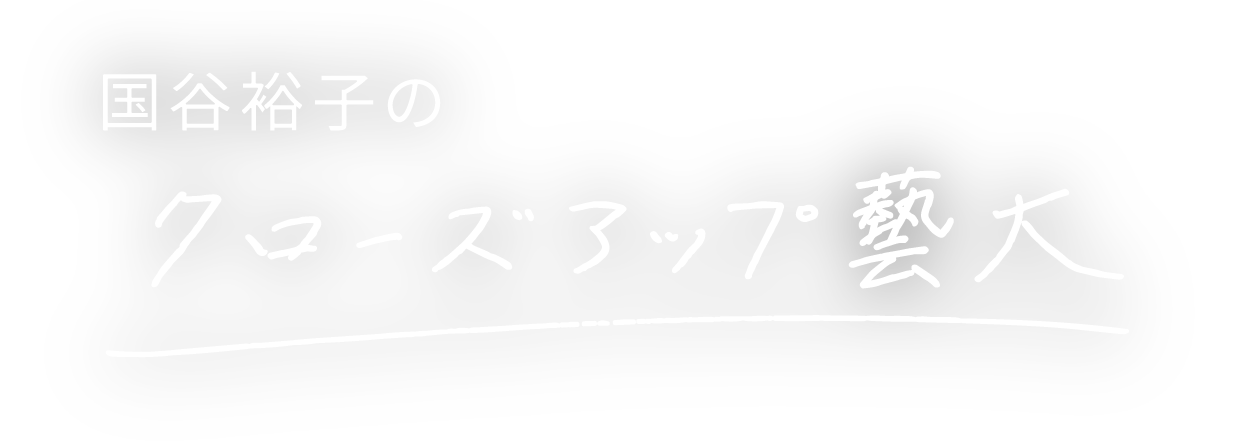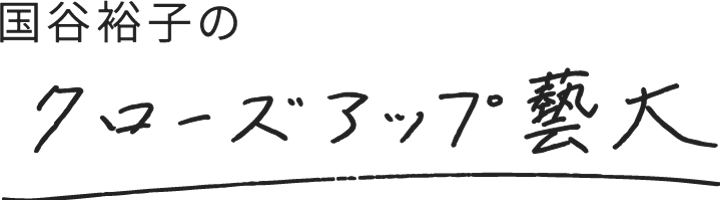- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第九回 小沢剛 美術学部先端芸術表現科教授
時間はかかるけれど、心に響くはず
国谷
先生の作品のなかにペットボトルを集めてそのプラスチックを絨毯にした「天空からの絨毯」があります。私は今、サステイナビリティとか地球温暖化に関する取材や啓発活動をしていますが、先生はそれを2006年になさったって聞いて…。今でこそ使い捨てプラスチックが問題になっていますが、その頃は全く問題になっていなかったのでは。
小沢
全く話題にならなかったです。最初はチベットのカイラスという聖山でひたすら集めて、天津の工場で絨毯にしてもらいました。そのあとも、対馬海峡沿いに漂流ゴミが海流にのって流れ着くのを知って、釜山、青島、対馬と、3カ国の海沿いで拾ったペットボトルでも1枚作りました。けっこう大変でした。
国谷
その着眼点がすばらしい。非常に異質ですよね、あれだけ美しく雄大な自然のなかにペットボトルが落ちている。それを見てアクションを起こそうと思い、さらにアートにつなげる。なかなかそういう発想はできないと思います。
その絨毯はどういうふうにディスプレイなさったんですか、作品として?

小沢
最終的に一枚の大きな絨毯を壁に展示しようと思っていました。拾ったペットボトルはリサイクル繊維となり絨毯へと加工しました。依頼した中国?天津の工場で、その作業工程に立ち会っていたのですが、ちょっと目を離した隙に、完成した絨毯を工員さんが、勝手にジョキジョキ切ってしまって。なんじゃこりゃ!?みたいな、細長い小さなマットみたいなもの10枚ぐらいになっていて、けっこうショックでした。言葉が通じないって怖いですよね。
展示はその細長いマットを天井から吊って、鑑賞するようにしたんですけど、まあちょっと無理がありましたね。
国谷
でも、これだけのことをするにはお金集めも大変ですし、プロジェクト全体をマネージするには力業が要ります。理解は得られましたか?
小沢
そうですね。そのときは財団がバックアップしてくれて、対馬に行ったときはヨーロッパで展覧会があったから確かルクセンブルクの美術館が出してくれた。
国谷
ニュースで、大気中の二酸化炭素の濃度が過去最高になったと伝えていました。このまま行くと今世紀末までに平均気温が3.5度上昇するそうです。今すでに平均気温が1.1度上昇していますが、1.1度上昇しただけであれほどの洪水が起きたり、夏の暑さも酷いのに…。
小沢
最悪ですね。
国谷
ですから何かハッとさせてくれるような、それこそ人間の意識改革につながるような何かを、芸術の力でできないかと、いつも私は思っているんです。
小沢
即効性はないけれど、心に響くはずなんで。誰か強く受け止めた人の行動を変えるはずだと。それを望みますけどね、僕は。
どうしたらいいのかわからない最悪な時代
国谷
先生は現代が抱える矛盾みたいなものに鋭い眼差しを向けられています。今の社会はどういうふうに見えていますか?
小沢
もう最悪な時代になってる。戦前みたい。だけど大昔からサイクルがあって、いいときもあれば悪いときもある。人間の生きてる世界ってそういうものだから。人間はどん底に行ってまた這い上がる力を秘めてるはずだから。
国谷
今は“底”ですか?
小沢
そっちに向かっているんじゃないですか。世界の政治は何もよくないし、戦争はいつ起きてもおかしくないし、自由は失われ始めているし。ここ何ヶ月かでいろんな国の美術関係者とかと話していても、みんな「まともだった日本が今こんなにひどくなってるの? 大丈夫?」みたいな話をしますけどね。「あいちトリエンナーレ」の問題とか、そのあとの文化庁の予算がストップされた問題だとか。まあみんな冷静に見てると思いますけどね。今起きてることを。
国谷
「表現の自由」ということについても?
小沢
総合的にすごく関心があることだけれど、昔の60年代70年代みたいなデモをやってもしょうがないだろうし。何かいい突破口はないかと考えたり、動いたりしていますけど、なかなかだめですね。今より良くなる要素は全く見えない。どう解決したらいいのかとあがいています。

国谷
悪くなっている要因は何ですか?
小沢
要因ですか? えっと、いや、誰かのせいにすれば楽ですよね。わかりやすい悪者がいればいいんですけど限定はしにくい。むしろ要因は拡散しているんじゃないですかね。まあ僕のなかにもあるのかも知れないし。そういう止めようのない墜ち方をしているんじゃないかなと感じます。
国谷
先生がバックパッカーで崩壊一カ月前までいらしたベルリンの壁が崩壊して、30年が経ちました。協調的な世界とかユーフォリアみたいなものができるんじゃないかと一時は思いましたよね。国連の時代が来るとか。
小沢
思いましたよね。EUが統合されて冷戦が終わり、良くなるしかないと。
国谷
ところが、アメリカが超大国になって他の国々に介入してぐちゃぐちゃにした。確かに発展途上国は経済成長はしたけれども、世の中は分断されてしまった。自分が良ければいいみたいな。
今は環境問題もあって、なんでこんな不寛容な居心地の悪い社会になってしまったのだろうと、嫌になってしまいます。すいません、こんなこと言って。
小沢
そういうときはね、雄大な利根川の流れでも見ませんか(笑)。

ぼんやり生きてると変な絵を描かされてしまう
国谷
本の中で、先生は「アートの位置づけを社会のなかの自由の位置づけの尺度にして捉えることができるだろう」と書かれています。これを読んだときに思い浮かんだのは、「あいちトリエンナーレ」のことでした。
小沢
アートの位置付けが社会の寛容さと関係しているのは確かだと思うし、それが成熟なのか、どうなんだろう。
国谷
表現を社会がどこまで受け入れてくれるかっていうのは意外と脆いのかもしれないですね。
小沢
そうです。すごい脆いと思います。すぐひびが入る。だからそれを意識して生きていかなきゃいけない。
僕は戦前のことをけっこう調べたことがあるんですけれど、多くの作家はあまり危機感を持っていなかったと思うんですよ。戦ってた美術家とか文学者は少なかった。まあ一部、小林多喜二みたいに拷問にあっちゃう人や、かなり過激な人たちもいましたけれど、それ以外の動きってあんまりなかったみたいなんですよね。
戦争に協力しないと絵の具も配給されないんで、当時かなりとんがって活動していた絵描きたちも、手のひらを返したように戦争に協力するような絵ばっかり描くようになる。音楽家や文学者も、小学校の教科書に載ってたような有名な作家はみんな協力してた。それを大人になってから知って、けっこうショックでしたね。そういうのを調べていると、ぼんやり生きているとそんな変な絵を描かされてしまうんだということが見えてくる。僕はそんな生き方はしたくないなと思っています。
時代のなかで生きる。消費されるだけでなく
 ベジタブル?ウェポン―さんまのつみれ鍋/東京
ベジタブル?ウェポン―さんまのつみれ鍋/東京
Vegetable Weapon: Saury fish ball hot pot / Tokyo
2001
所蔵:国立国際美術館、大阪
Collection of The National Museum of Art, Osaka
国谷
「ベジタブル?ウェポン」(2001年)は様々な国や地域に出て行ってインタビューし、食文化も学び、最後は食べるという作品ですね。
小沢
まずモデルとなる地元の方にインタビューして好きな地元料理を教えてもらって、一緒に地元のマーケットに食材を買いに行き、その食材を使って銃を作って撮影する。その後、それを解体して皆で料理して、食べながら語り合う場を設けるっていう。
国谷
これは、2001年の作品ですね。ちょうど同時多発テロ事件が起きた年です。
小沢
それで、暴力に対抗するものっていうのを考えたんです。最初はアジアの国々、それからアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ大陸と様々な地域で行ってきました。戦争とかテロの原因って、よその文化を理解していない、そういう無知や偏見が根底にあるから。互いにいろんな文化を知る、その入り口としては食文化を楽しむっていうのは入りやすいところかなって。で、それを形に持っていく、武器というものに対する批判を美しく形にするにはどうすればいいのかと考えて。
国谷
そうですか。やはり先生の作品は、時代と社会情勢を考えて観ないと。
小沢
時代のなかで生きている感じなんで。でも、その時代で消費されるだけはなく。
国谷
普遍的なメッセージがあるわけですね。

どこにアートのネタがあるかわからない
国谷
先生は学生たちに何をどう教えていらっしゃるんですか?
小沢
最近やったのはリサーチ。取手のエリアをリサーチして、それを作品化しましょうっていう課題です。
ここに通ってくる学生は駅からバスに乗って来てここで降りるから、駅前から学校までの間のことは知らない、関係ないんですよね。
国谷
駅から5.9キロもある。
小沢
その広いエリアの歴史とか地形とか自然とかを調べてみて、それを元に作品化しようという課題だったんです。川には昔は渡し船があったのでその辺のことを調べたり、釣り人と交流して語り合ってた学生もいたし。そんな課題をやっています。どこにアートのネタがあるかわからないから、その可能性を拡張するような。
さっきも旅をした話をしましたけれど、ものすごく遠いところに何かあるかもしれないけれど、ものすごく近い、見てないところもちゃんと見ようって。だって、学校のバス停のもう一つ先って、絶対に誰も行かないじゃないですか。でもあえてそこに行って、何か発見するっていう。こういう美術という仕事をしてるんだから、無駄なことをやってみたらどうかなって。
国谷
今の学生は、苦手じゃないですか?
小沢
だからあえてやってみたり。
国谷
自分ではしないようなことをすると接点が広がりますよね。地域との接点も。
小沢
そう思いますよ。とにかく知らない人と会ったりとか、インタビューすることは大事だから。
一枚の絵が飢える子どもを救うこともできる
国谷
そういえばお母様がいいことをおっしゃっていたそうですね。「一枚の絵が飢える子どもを救うこともできるんだ」と。
小沢
僕はそう信じていたんですけど、母親は覚えてないみたいです。僕にとっては忘れられない言葉です。
国谷
すてきな言葉です。ですから一本の鉛筆でできることを大事にしている。
小沢
してます。描くのは大事だと思って。
国谷
卒業してアーティストとして先が見えなかった時期も、一日一枚のドローイングを自分に課していたそうですね。
小沢
やってました。不安だから。
国谷
先生が苦しんだような、この先どうなっちゃうんだろうっていう時代を、学生たちはどうやって乗り越えたらいいと思いますか?
小沢
月並みですけど、継続は力になる…けど、それだけじゃないのかもしれないけど。

【対談後記】
他の科と何が違うのか。“材料が決まっていない。自分の作りたいもの、アイディアがあってそれを表現する一番合う材料を探すのが先端”と答えた小沢先生。とにかく知らない人と会ったり、インタビュー、リサーチすることが大事で、自分は社会学が好きだと話してくれました。
気になっていた「呪」という字。次の作品?と聞くと首を横に振られました。9月を目指して構想中。“壮大、めちゃめちゃ大きい”とだけ教えてくれました。
【プロフィール】
小沢剛
美術学部先端芸術表現科 教授
1965年東京生まれ。1989年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。1991年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(壁画)修士課程修了。2012年より本学美術学部准教授。大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻教授を経て現職。
在学中から、風景の中に自作の地蔵を建立し、写真に収める《地蔵建立》開始。93年から牛乳箱を用いた超小型移動式ギャラリー《なすび画廊》や《相談芸術》を開始。99年には日本美術史の名作を醤油でリメイクした《醤油画資料館》を制作。2001年より女性が野菜で出来た武器を持つポートレート写真のシリーズ《ベジタブル?ウェポン》を制作。2004年に個展「同時に答えろYesとNo!」(森美術館)、09年に個展「透明ランナーは走りつづける」(広島市現代美術館)、2018年に個展「不完全―パラレルな美術史」(千葉市美術館)を開催。
https://www.ozawatsuyoshi.net/
撮影:寺田健人
- 1
- 2