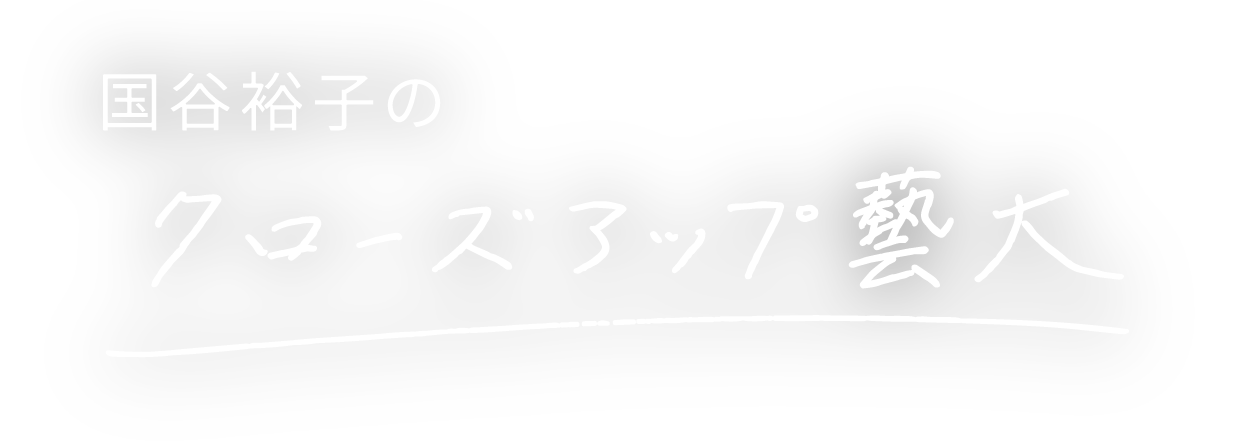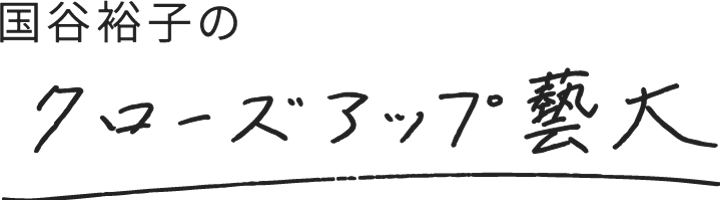第十二回 箭内道彦 美術学部デザイン科教授
言葉の力を信じる
国谷
箭内さんは、言葉の力は信じていますか?
箭内
とても信じています。言葉にならないものの力も併せて信じています。言葉って、黙ってて口にしなかったら成仏しないものだと思うんです。だから、音声になる言葉だったり文字になる言葉はもちろんですけれど、それ以前の沈黙を含めて僕は信じています。
映画監督の是枝裕和さんと昔仕事した時に、是枝さんがインタビューをしながらカメラで撮っているんですけれど、そこで相手の人が質問に答えられなくて。でも是枝さんは助け船一つ出さずに、困っている顔を何分間も撮り続けているんです。そういうことも含めて、シャープに言葉が出るだけじゃない、五分間考えて出たというそこもセットで、言葉の力ってなんかあるんじゃないかなと思っています。
「わからない」って言葉を発する人がいてもいい。だけど僕は「難しい」って言葉はあん まり好きじゃなくて──「難しいですね、これ」って言うと止まっちゃうんですよね。でも「わからない」っていうのは「じゃあどうしようか」っていうことの始まりになる気がして。なんか言葉の力っていうのと話がずれてしまったんですけど。
国谷
今はLINEなどで一行のコミュニケーションみたいなものが頻繁に行われています。言葉が軽いというか、すぐに忘れられていく。言葉が槍のように人を傷つけたりしていますが、一方で、みんなが言葉を信じなくなってきています。その人でなければ言えない言葉だとか、わからないながら考えて考えてひねり出した言葉には、力があると思うんですけれど、そうした言葉が出るまで待つことをしなくなっている。

箭内
一部の政治家が言葉の価値をどんどん軽くしてしまってますよね。しかも積極的に早合点していく人も多いですしね。なんか、言葉の一行目だけを見て、それでもう瞬間沸騰しちゃうじゃないですか。もちろん自分の中にもそれがある。
国谷
そうですね。箭内さんは、言葉で勝負されています。
箭内
僕ですか? そうですね。
国谷
広告など本当に少ない言葉で。
箭内
僕はですね、元々短い言葉が好きなんですよ。歌の歌詞であるとか、谷川俊太郎さんの詩であるとか。すごく難しいことを簡単に言ってくれる言葉が好きなので、八木重吉もすごく好きです。だからできるだけ、そこに近づくことはできないけど、そうあろうとは思っていて。簡単なことを難しく言うのではなくて、難しいことをできるだけ簡単に説明できるようにっていうのは考えています。もちろん、なかなかそうは上手くいかないですけどね。
問いかけはする。しかし、答えは話さない
国谷
箭内さんはデザイン科の先生をされているわけですが、教えている姿よりも社会との関わりのほうのイメージが強いので、いったいこの方は大学で十八歳から二十代前半ぐらいの若者に対して、何を教えているんだろうって知りたいと思っているんですけれど。
箭内
痛いところを突かれてしまいましたね(笑)。そういう質問来たらいやだなと思っていたんですよ。その質問に答えるとすれば、僕は多分、藝大の教員の中で一番教えるの上手くないと思います。
国谷
何を伝えたいと思っているのか、何を与えたいのか、何を受け取ってもらいたいと思っているのか。そのためにどういう授業をされているのか知りたい。
箭内
そうですね。僕は自分が藝大の学生だった当時は、申し訳ないけど何一つ先生に教えてもらってないと記憶しているんです。でもそれが良かったなって今も思っています。それは、自由に楽しく四年間暮らせたっていうわけじゃなくて、自分で何かを見つけなきゃいけないという、ものすごい焦燥感に包まれていたからです。答えを教えてくれる先生はいらないって、僕は思っていて──それは他の先生方がものすごくしっかり教えられているから僕はそういうオルタナティブなポジションにいられるんですけど──できるだけ答えを話さないようにすることを意識しています。
国谷
でも、問いかけはするんですよね。
箭内
問いかけはします。授業でやっているのは、例えば二年生に出している課題は、「チャーミングに異を唱えよ」っていう課題。この世の中に生きていく中で自分が何か気が付いた、あれはおかしいんじゃないか、あれに不満があるっていうことを、まず見つけてくるんですね。で、それを、拳を振り上げて怒りを表明して「絶対反対!」って言うんじゃなくて、なんかみんながクスっと笑うような、賛成派も反対派もそのクリエイティブで一つになれちゃうような、そういう答え方を提示しなさい、という授業をやっています。
国谷
え! 難しそう。でも大事なことですよね。それができたらみんなまろやかになる。
箭内
今すごく、とても必要なことなんですよね。怒りをまっすぐに表明するのも尊いんだけど、それをやっちゃうとそれこそ線が引かれてしまういうかね、そうじゃない人たちからすると、ちょっと怖い、自分はあそこには入れないと思ってしまうんですよね。それを「チャーミングに」っていうのは、多分広告の手法でもあると思います。あと三年生に出している課題は、「世界平和を実現するデザイン」。何を作ったら世界は本当に平和になるのかっていうもので、それを具体的に作るんですよ。
国谷
へえー。
箭内
「映像論」という授業には、さっきの是枝さんも非常勤講師で来てもらったり、お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんにも来てもらったり、脚本家の宮藤官九郎さんが来たり、豪華なんですよ。豪華っていうか、なんていうんですかね、そういう人たちに会わせてみたいんですよね、みんなを。
国谷
とても嬉しいだろうな。触発されるでしょうね。
箭内
あとやってるのは、ラップを作る授業。「自分が今思っていることをラップにしてみんなの前で歌いなさい」って。RHYMESTER のMummy-D を毎年講師に呼んでます。そんなのどこがデザイン科なんだって感じですけど(笑)。そのあと、そこに映像を付けていくんですよ。みんな活き活きやっています。
最近やって一番面白かったのは、それぞれに三十分のラジオ番組を作れっていう課題。そこで自分が今思っていることを話してもいいし、自分がものを作る時に感じていることを話してもいいし、自分が好きな音楽をかけてその理由をしゃべってもなんでもいいんです。みんな、誰にも言わなかったことを初めて言葉にする時の緊張とざわめきと、心地よさみたいなものを感じて、ちょっと病みつきになってますね。それこそ言葉にすることによって、です。

国谷
そうですか。
箭内
第二弾作りましたって送ってくる学生もいたりして。色を塗ったり立体を作ったりということでは全然ないんだけど、そういう経験が、なんていうか、デザインがものを伝えたり何かを変えていこうという仕事なのだとしたら、外側にあるそういうこととの共通性を通じていつか、個人の中で「開通」されていくと思うんですよね。なんかそういうのをえらい先生に見つかったら怒られるだろうなと思いながら勝手にやってます。
国谷
そういうとてもユニークな授業で、今「開通」とおっしゃいましたが、箭内さんは伝えようというよりも、何だろう、与えるということでもないですよね。
箭内
そうですね、広告っていうのは、一つは応援することだと僕は思っていて。商品を応援する、企業を応援する、それを使う人を応援する、その商品がある社会を応援する。もう一つ、広告は、その対象の魅力を最大化させて世の中に放つことって思っています。だから学生たちが、昨日と違った表情になるというのがすごく好きで。わ! これやってみたら、なんかキラキラしちゃってる、みたいなね。なんかその体験を積ませたい、ある種の成功体験だと思うんですけど。それが表現が機能しているっていう状態だと思うんです。
自分で自分を覚醒させる
国谷
箭内さんは著書の中で、自分の十代二十代三十代のことをバネに四十代五十代を生きているとお書きになっていますが、自分が藝大生だった時にはあまり教えてもらった経験がないともおっしゃっています。そういう体験を踏まえて、若い人たちが今体験すべきことを大事にしたい、そういう思いがあるんですか?
箭内
それは強くありますね。僕の大学の四年間は全て挫折への四年間だったので。
国谷
本当ですか?
箭内
本当です。自分が学生の頃の成績表とか発掘されたら大変だなって思うくらい、多分一番悪い成績で大学に戻ってきてる教員だと思います(笑)。
国谷
大学にいる間は自己肯定感が全く高まらなかったってことですか?
箭内
そうですね。先生方からも褒められなかったし、自分でも何一つやり切れていないなと思っていて。それは、サボってプラプラしてたとかじゃないですけど、何かを見つけられなかったみたいなことがあって。だからこそ、その復讐劇が今も続いているという(笑)。それはそれで面白いなと自分でも思うんで、だから課題の成績が悪い学生に、「課題の成績が悪いことをどうバネにするか」っていうヒントは与えたいなと思うし、成績が悪いことをサラッと流しちゃうんじゃなくて、ずしんと重たく感じてほしいなという話はしています。
国谷
そのユニークな課題を学生たちが自分でやるということは、自分が学生の時にそういうものがあったらよかったなって思いからですか。箭内さんからすると藝大の授業のどこが悪かったのですか?
箭内
いや、全然悪くはないんですよ。放っておかれてよかったなって思うし、何も教えてもらえなくてよかった。
国谷
何も教えられなかった?
箭内
そういう学校だったんですよね、昔は。学生も、教えてほしい教えてほしい、授業料分ちゃんと指導してほしいなんて思う学生もいなくて。教えてほしい教えてほしいになっちゃうと、教える人と教わる側の絶対的な関係みたいなのが生まれてしまうじゃないですか。それが僕はいやだなと思う。
国谷
上下関係にはなりたくない。
箭内
この学校の素晴らしさは、充実した教員陣だけじゃなくて、難関をかいくぐってきた、だけど違う夢を見ている仲間たちが隣にいて、同じ課題、例えば「チャーミングに異を唱えよ」って言われても、違う答え方をする仲間がデザイン科だと四十五人いる。それがやっぱりかけがえのない体験なんですよね。僕らはそれのただ管理人なだけなんですよ。
もちろんそうじゃない先生方もたくさんいるし、「お前それ給料泥棒だろう」って言われるからちょっと危ないんだけど(笑)。でも僕は、ちょっと背中を押したり刺激を与えたりする存在でいた。でもその「ちょっと」が重要だから、僕の仕事の現場を見たいっていう学生はどんどん連れて行ったりもしています。それは背中を見せるとかそんな恰好いいことではないんですけど、僕が慌ててたり困ってたり悩んでたり、恰好よく解決したりっていう、そういうドキュメンタリーを生で見てほしいなって思っています。
国谷
面白いですね。
箭内
青い。青いんだと思いますよ。甘っちょろいんだと思いますよ。これ読まれたら「お前それで教授務まんないよ」って絶対読んだら言われちゃいます。
国谷
学生が自分と向き合うような授業をされている。自分で自分を覚醒させないといけない、自己覚醒させる授業をされているような感じがします。
箭内
それは狙っていると思います。でもその時の快感を感じてほしいんですよね、学生たちに。怖さと驚きと気持ちよさみたいな。それはこれから一生、ものを作っていく時の何か大事なお守りになる気がしていて。ちゃんとしたことを教える先生はたくさんいるし、そういう先生から学生たちはちゃんとしたことをしっかり教わっているんで。デザイン科は研究室ごとにテーマ設定がされているんですけど、僕は「Design Alternative」っていうところなんですよ。だからみんながデザインだって言っていないようなものもデザインなんだって考える。例えば、美味しそうなお弁当をお母さんが作ったらそれもデザインだみたいなね。
国谷
そのように覚醒された人たちが世の中に出て行くと、自分の身のまわり、自分の置かれた状況を見て、我々の社会はもっと変わっていかないといけないと、能動的にデザイン力を生かした活動をどんどんやってくれそうな気がします。さきほどおっしゃった、壁の色を黄色にするのか赤にするのかの選択ではなく、青にしてしまうとか、壁をそもそもなくすという提案をするなど、オルタナティブを常に考えるっていうことが、実行力につながる。
箭内
そうですね。実行力、実現力ですね。国谷さんがおっしゃっていたように、何パーセントの人がどう動くかで世界を変えられるなら、自分が大学で出会ったいろんな学生たちが、その何パーセントの中でね、力を発揮する一員になってほしいという勝手な願いは持っちゃっていますね。今日、国谷さんと話しての発見でしたけど、自分でもちょっと驚きでした。

表現者として自由になれる「開通」体験
国谷
熊倉純子先生(大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻教授)は、藝大の教授になろうとは全く思っていなかったそうです。美術史を学ばれ、フランス語ができて、留学して。で、帰ってきて企業メセナのアルバイトを始めた。メセナが花盛りだった頃で、各地にいろんなホールとかができていった中で、だんだん地元市民とアートを結ぶアートマネジメントのような仕事をクリエイトしパイオニアになられた。彼女の中では、どうやったら、お金持ちじゃない人でもアートに出会えるのかっていう問いを、ずっとお持ちになっていた。
「クロ藝」をやらせていただいて非常に面白いのは、なんで今こういうものにこだわっているのかの背景には、一人ひとりの原体験、いいストーリー、いい問いがあるんです。そのストーリーに出会えると、この企画をやってよかったなって毎回思うんです。熊倉先生の場合、なぜお金持ちじゃないと芸術と出会えないのか、どうしたら誰でも出会えるようになるのかという「問い」でした。
箭内さんもきっとそうだと思うんですけど、人を動かすことの背景にはいいストーリーや原体験があります。

箭内
背景だけじゃなくてね、原体験と自分がやるべきこと、今やるべき発想っていうのを、さっき「開通」って言葉を使いましたけど、開通させることができた人と、できなかった人、そこで線引きされているのかもしれない。開通するともう楽なんですよ。自分のこれまでの人生が全部そのまま仕事になっていくじゃないですか。でも、学生ですら人生は人生、仕事は仕事、自分は自分、課題は課題ってどうしても分けちゃっている。大人になっても分けてる人はいますけど、そこの壁をバーンと壊せた人だけが、おそらくライフワークとしてクリエイティブという仕事を、それこそ持続可能になっていくのだと思います。終わらないんですよね、原体験の復讐劇、弔い合戦だから。
それがないまま、職業としてプロフェッショナルを名乗っても、どうしても何のためにそれをやってるのかという「根」がない。でも、その壁と壁の間を自然に接続できた人はいいんだけど、別のものって考えてしまってる学生だったり社会に出た若い人が多いんですよね。そこをつなぐだけでみんな猛烈に何百倍も自由になれると思います。
国谷
そうか! 「開通」ってそういう意味なんですか。だから日比野さんもごく自然に障がい者施設に泊まり込んで、そこでアートプロジェクトをやる。はじめは障がいを持った方が色をひたすら塗っている、その脇にいて自分も刺激を受ける。でもその人は色を塗るのが好きなのではなくて、色鉛筆を削るのが本当は好きだからなんです。でも違ったものに触れることで自分もまた触発されると話していらっしゃる。体験の中の、何かざらついたものに、自分が表現すべきもののヒントがあると。今、箭内さんのお話をうかがって、ああそうかと思ったのは、体験がつながってくると表現者として自由になれる。
箭内
もうエンドレスモードに入るんですよね。
国谷
入るんですか。
箭内
日比野さんもそこがつながってるから、障がい者の方々のところに行く。それはモチベーションがあるとか、行くことが大切だからとか、行かなければいけないからとか、そういうことじゃないってことが大事なんです。SDGsのこともそうだし、いろんな、人間全員そこが開通されたらすごくいい。
箭内道彦の「開通」体験
国谷
箭内さんの「開通」体験は何ですか?
箭内
僕は三年浪人をしています。二浪目までは「明日試験でも受かるよ」みたいに言われてたまじめな浪人生だったんですよ。まあ二浪目の受験でも受かんなくて、もうこれはどうやったら受かるんだって思った時に、本当に自分が描きたくて描いてる絵じゃないことに気が付いた。受験の勉強のため、受かるためにやってることだったって。まあそれで受かる人もたくさんいるんですけど(笑)。その描くことを一切楽しんでいないことに気が付いて、それで描きたくなるまで描くのを止めようと思ったんです。それで実家に帰って、家業がお菓子屋牛乳屋だったんですけど、それを手伝うというか、継いでるような感じでやっていたんです。
当時のデザイン科は入試倍率五十倍だったんで、僕は五十年受けようって決めたんですよ。五十年受ければ一回受かるっていう計算でしょって、自分の中でその時ぽーんと思えて。それで気持ちが楽になって、一年間何も描かないで藝大の試験会場に一時間遅刻して入ったんですけど、急に何も準備してない自分っていうものが怖くなっちゃって。わざとやってたくせにね。だけど席についたら、「受かんなくてもいいから描きたーい!」っていう、描きたいっていう気持ちが生まれて初めて湧いてきた。それはそこで知ったんですよね。その初期衝動を常に持ち続けてはいます。まあストーリーにはなっていない話ではあるんですけど、大きな体験ではありました。
だから卒業してからもそこが基準になっていますね。あれは本当にありがたかったです。なんか自分にとっては、そこの壁を越えるためには、この体験が必要だったんだなあと思います。
国谷
学生たちに、どんどん開通体験というか、目の色が変わってくる、そういう体験をさせたいという思いを持ちながら向き合っていらっしゃる。楽しみですね。
企業と藝大との連携
国谷
企業にはもっと藝大と連携すると面白いことができると思ってほしいし、自分たちが触発される場所だと思ってもらえるようになったらいいなと思います。もちろん、企業色に染まるという意味ではなく。藝大を支えてくれるような関係を持てるように企業とつながっていけたらいいですね。
箭内
あれもできます、これもできますみたいな、なんか藝大にあるものを企業に捧げますモードになっちゃうと、最初の入り口が良くないと思うんです。そうしたら、もっとこれしてください、あれしてくださいって、こうしてもらわないと利益になりませんとかってなっちゃう。利益にならないかもしれないけど、この人と付き合いたい、そう思わせたいですよね。
国谷
そうそう、それですね!
箭内
そのためには、そもそも大事なのは我々がもっとキラキラ輝いて、企業から告白を受けるような存在にならないといけないし、基本はそこしかないと思うんですよね。企業のほうが直観で、藝大と何かやりたいと思ってくれるような存在にならないと。本当は、国谷さんは間をつなぐ存在だから何かいいセールスシートがあるとか、武器をお渡しできるといいんだけど、そういうメニューを作るのはすごく危険な感じがして。藝大は、メニューではなく、「オレンジじゃなくて青がいいよ」って言えるアートの視点をお渡しすることはできますよね。
 2019年度辞令交付の際の記念写真。中央が箭内教授、右端が国谷理事
2019年度辞令交付の際の記念写真。中央が箭内教授、右端が国谷理事
【対談後記】
箭内さんがおっしゃった「〝ねばならない〞っていう重い足かせや、悲壮感の中で新しい時代を作っていこうっていうのは気高くはあるけど難しい」。報道の世界に長い間身を置いていた中で、課題を抽出し、背景をみて解決策の提示を繰り返してきただけに自分には「ねばならない」話法が染みついているのではと、とても考えさせられました。
進む環境の劣化、格差の拡大、テレビを離れて取り組んでいるSDGsは持続可能な社会を目指していて、目標の二〇三〇年に向けてこの数年が鍵とされています。「もし持続可能な地球と社会が作り出されたらこんな素敵なことが起き、こんな良い気持ちになれる」をクリエイティブの力を使って力強く発信できたらどうなるだろう。多くの人々が、今、求められている大胆な経済モデルの変革に、合理的な理由ではなく情緒的な理由で支持をするようになり、日本が持つ科学の力とアートの力が共創する形でダイナミックに動き出す原動力になっていくのではないかと妄想し始めました。
一方で喫緊の足元の課題は若手芸術家の支援ですが、まだ思うようにムーブメントを創れていません。皆様のご協力を改めて強くお願いいたします。
【プロフィール】
箭内道彦
美術学部デザイン科教授
1964年、福島県郡山市生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。クリエイティブディレクター。博報堂を経て、「風とロック」設立。タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」キャンペーン、リクルート「ゼクシィ」、サントリー「ほろよい」、グリコ、パルコ、資生堂など数々の話題の広告を手掛ける。「月刊 風とロック」発行人。福島県クリエイティブディレクター、渋谷のラジオ名誉局長、ロックバンドの猪苗代湖ズのギタリストでもある。2016年、東京藝術大学美術学部デザイン科准教授、2019年より現職。学長特命(広報?ブランディング戦略担当)も務める。
- 1
- 2