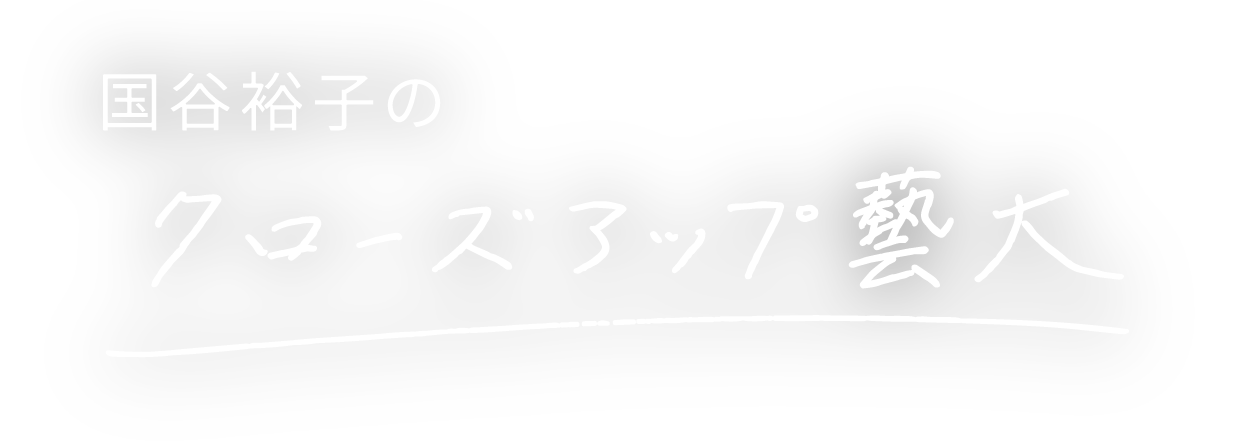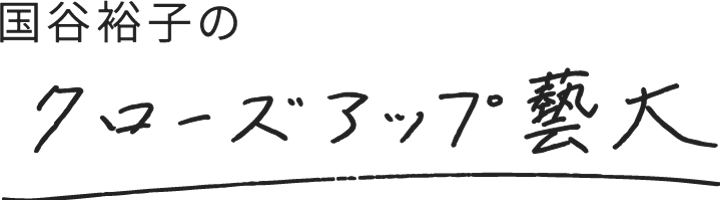第十三回 青木淳 美術学部建築科教授
京都市京セラ美術館のリニューアルと館長就任
青木
京都市京セラ美術館もね、こういう道というか通路のデザインにしたわけです。
国谷
美術館に吸い込まれるような感じがします。地下をちょっと掘ってスロープを作り、下から入るようになっています。

京都市京セラ美術館??Daici Ano
青木
太鼓橋をひっくり返した形は馬見原橋と同じです。その一番低いところから入って、まっすぐ大陳列室に上って行って、そのまま反対側の日本庭園に抜けることができます。美術館の真ん中に道が通っているんです。途中の大陳列室は大がかりな展示もパフォーマンスもできる。実はいろんなことが可能です。設計者が先回りして使えるようにガチガチに作らなくても、人って使えそうなところを見つけて活用するものだと思うんですよ。
国谷
あそこでミュージカルの撮影とかしたら素敵だなって思って。踊りたくなりますよ。誰も見ていなかったら私…。館長にも就任されました。改修を行った建築家がそこの館長になるのはあまり例がありません。
青木
聞いたことないですね。
国谷
通常は、いろんな美術館を巡ってキャリアを積んで来られた方が館長になるわけですよね?
青木
そうですね。あるいは、お役所から回ってきます。だから頼まれた時にはびっくりしました。何かの間違いだと思いました。この美術館の保存?再生プロジェクトは2015年に始まり、何をどういうふうにしたいのかを聞いたり、ディスカッションしたりしながら、空間がどうあるべきかを決めてきました。僕たち建築家はハードの側からソフトとハードの関係を考えます。ソフトがないとハードは成立しません。でもそれと同時に、ハードがどんなソフトを生んでいくものか、ということも考えます。この美術館は、その過去の姿を否定するわけでもなく、また全く新しいものをコントラストをつけて付加するわけでもなく、過去と今との間で何とか折り合いを付けて、地層を重ねるようにして、全体のあり方を一変させようとしました。その考え方がこれからの運営のイメージと合ったらしいんですね。だから僕に、今度は違う立場で関わってほしいと。建築で考えてきたことに、違う側面から向き合ってほしいと。
国谷
先生は、自分は館長じゃない、ディレクターだとおっしゃっています。私はその区別がよくわからないのですが。
青木
館長という言葉は、上意下達で組織を動かす人というニュアンスが強いですね。でも、組織は別々の関心で働いている人から成り立っています。美術館だったら、展覧会を企画する学芸員、総務や広報、ワークショップなどを担当するラーニングの人、清掃する人、受付をする人、カフェやショップの人といろんな人がいるでしょう。その全員がうまく噛み合わないと美術館はうまくいかないので、そこで皆がうまく連動するようにもっていく。そういう意味で、方向付けをする=ディレクション仕事なので、ディレクターと呼んでほしいと言っています。
国谷
そうすると美術館ではディレクターとして、そこで働いている方のいろんな意見がある場にいらっしゃって…。
青木
交通整理をする。
国谷
お巡りさんみたいですね(笑)。
青木
いちばん危険な交差点に立っている(笑)。いろんな立場の人がいるから意見がぶつかりますよね。その中で、ぶつかりながらも、大事故にならないような、全体としてはいい方向を作れればと。
国谷
でもその方向は先生が決断されるのでしょう?
青木
僕が、というよりは、もっと大きな理念が、という感じですね。この美術館は、京都市民から税金という形で、市が預かったお金で運営されています。だから、市民の文化活動に貢献するものでなくてはなりません。なのに、まだ美術館に足を踏み入れたことさえない市民も多いんです。つまり、皆等しく文化活動を行なう権利を持っているのに、それが必ずしも与えられていない。もっともっと多くの人にとって、ここが無いと生きていけないと思えるくらいの、文化を核とした交流の場所になりえるか、がひとつの大きな判断基準なんです。
国谷
このタイミングで全く違う分野の方が館長になるというのは、「美術館は何のために存在しているのか」ということが、今、問われているからでしょうか。

青木
そうだと思います。美術館は、文化財産を収集、保存、調査研究、普及、展示する機関でしたし、これからもその基軸は変わらないと思います。でも、そういうことを続けていくことの意義を多くの人々にわかってもらうという努力も、それとセットになっていなくてはなりません。少なくとも日本の場合、そもそもその意義が根付いていないんですから。なぜかというと、その理由のひとつは、文化財産ということが、かなり狭い意味でしか捉えられていないから、と思っています。じっさい、このコロナ禍で美術館は不要不急の施設ではないと判断されてしまいましたね。
国谷
先生は美術館について、特権階級の余裕のある美術愛好家のような人が来ている、そういう特権的な場所であるとおっしゃっています。
青木
ええ、特権階級と言っても、お金持ちとか権力者いう意味じゃなく、いわゆる美術愛好家という限られた層、という意味です。もちろん美術愛好家が来てくれなければ美術館はなりたちませんが、文化って、なにも高尚なものだけではなく、衣食住を含めた、もっと僕たちの日常の中にもあるわけでしょう。美術館が、文化?芸術を媒介とした人々にとっての居間、あるいは「原っぱ」のような場所に変わっていったらいいなと思います。
国谷
美術館は、よく考えると不思議な場所ですよね。国や文化の違いを越えていろんなアート作品に出会える場所だし、時間軸もさかのぼって自分がその時代のアートと向きあえる。そういう意味では、美術館自体がいろいろなものをフラットに議論したりする場に適しているのではないでしょうか。
青木
ええ。これは私見ですけど、芸術って、自分という殻から自由にさせてくれるコトやモノだと思うんです。だから美術館は、自分と違う感覚や価値観と、そう、フラットに交差できる場所であってほしいですね。
自分がデザインする土壌をデザインする
国谷
以前のインタビューで、先生がデザインの置かれている今の状況について危惧されています。「デザインは常に他者から依頼されているわけで、自分から選んだ領域ではない。僕らはその土壌の中でやってきたが今はその場が荒れちゃっている。若い人たちには自分で土壌を探す、デザインすることが求められると思う。そこに生まれる新しい世界に期待している」。これは具体的に、どういうことなのでしょう。
青木
ああ、あんまりうまく言えてないですねえ…。僕たちの世代くらいまでは建築家が社会に守られていた、必要とされていたという感じがあります。つまり、美術館を作るとか図書館を作るとなったら、それには当然建築家が必要だと思われていた。なんでかというと、「美術館としてこうあったらいい」というものがまだあやふやで、まだまだもっといいものがある、まだまだ可能性があると思われていたからです。建築家には、まだない「その次」を作ることが期待されていました。今までの因習とは違うものを作る創造性が期待されていた。ところが今は「いい美術館はこういうもの」とか、「いい図書館はこういうもの」「いい競技場はこういうもの」という型ができあがっていて、「もう新しいものは必要ないです。決まったものを作ってくれればいいです。余計なことはしないでください」と言われるようになってしまった。
国谷
そうなんですか。
青木
そう正面切って言われることは少ないけれど、いま、社会にそんな風潮が蔓延していますね。僕たちの世代は、よりいいものを作ろうと思っていたし、よりいいものが求められる土壌の中で生きてきたんです。ところが20年ぐらい前から状況が変わってきて、そういうことが求められなくなってきた。だから若い人たちが新たに登場できる機会も減っちゃったんです。僕が青森の美術館を設計したのは40歳ぐらいの時で、建築家としてはまだ若手といわれる年代でした。当時はまだ、若手でも選ばれる可能性があったし、じっさいに選ばれることもあったわけです。でも今はあまりなくなってきた。今ある仕事の多くは、経験のある人に「前と同じようないいものを作ってください」というもの。それでいいなら若い人たちは当然仕事がなくなるでしょう? チャンスが減っていく。そうなると生きていけないわけですから、現実的に。だから、まず、「美術館をデザインする」とかじゃなくて、「自分がデザインする土壌からデザイン」しなくちゃいけない。
建築家の仕事の可能性
国谷
こういうのが必要なんじゃないですかと提案するということでしょうか。
青木
そうですね、新しい領域を提案していく。例えばここ20年ぐらい「まちづくり」っていうのがけっこう盛んですけど、「まちづくり」って、都市設計とは違って、町の活性化という活動型の仕事のことを言います。こういうことは昔の建築家は積極的にはやらなかった。でも、建築を設計する仕事がなくなってしまったから、若い世代の中から、その町に移り住んで、ここをこうやったら町が楽しくなるじゃないかなって、リノベーションを提案したり自分でDIYをやったりする人たちが現れ出した。今はそういう時代で、自分たちが活動できる領域をまず作っていくところから始まります。すごい能力を持った人たちがいっぱいいます。でも、既定路線の先に行くのではない、「まだない建築」を作れる仕事があまりに少ない。僕の世代は、先輩たちの建築家と同じような領域でやっていけた最後かもしれません。だから、次の世代のことが気になるし、彼ら彼女らの未来を応援したいと思っています。
国谷
そういうことだったのですね。それは、設計家よりもその建物を施工する人たちのほうが力関係で上になってきて、設計者の価値が下がってきたということなのでしょうか?
青木
それはそれで、また別の文脈で言えることでしょうね。日本には昔、建築家はいませんでした。大工さんが設計し施工するものだったのが、明治以降、西欧の設計専業者つまり建築家という職能が輸入され、施工者に先立って設計者の地位を確立しようと、僕たちの大先輩たちががんばってきたわけです。その成果があって、公共建築については設計と施工を分離しなければならないというルールができました。でも、それは建前上のことで、実体は、設計者はあいかわらず施工者の設計能力にかなり頼っていました。それが最近になって、国土交通省が事業のタイプにあった形式をフレキシブルに選んで良いとしたので、施工者が設計をするというケースも増えてきました。ある意味では自業自得なのかもしれませんね。京都市京セラ美術館も、僕たちの設計は基本設計までで、その後の設計は施工者、ぼくたちは監修者という立ち位置でした。設計者が建築に関われる度合いは下がっています。

僕は海外の建築も設計することがあるんですけど、現地の施工実務や法律に疎いので、やはり「デザイン?アーキテクト」という設計全体からすれば部分的な関わり方になります。でもその場合でも、決定権はしっかりと与えられ、かつ建築家としての新しいアイデアや考え方が求められます。日本では反対に煙たがられます。
国谷
日本と同じようにある程度経済成長が止まったような国でも、より新しいものを求める国がある一方で、日本ではあまりそうではなくなっている。それはなぜでしょうか? とても深刻な問題だと思います。
青木
こちらが教えていただきたいくらいです(笑)。事は建築の中の話を越えて、社会全体に関わるすごく深刻な問題だと思います。ですから、建築家も頼まれたことをその枠組みの中で設計するのを越えて、もっと川上から関われるようにしていく努力が必要なのかもしれません。たまたま自分の設計した美術館の館長になってみて、そんなことを実感しています。
国谷
なるほど、先生自らが土壌を作っていらっしゃるんですね。
青木
できたら、そうありたいものですね。
「ブランドなんかの仕事をするべきでない」と言われ
青木
ところで、美術館のような公共建築だけでなく、ルイ?ヴィトンのような商業の仕事もしています。1998年がその最初で、世界を見渡しても当時はブランドの店舗は建築家がする仕事ではありませんでした。「建築家たるものブランドなんかの仕事をするべきでない」と怒られたりもしました。
国谷
それはなぜですか?
青木
建築家は、社会の先頭に立ってよりよい社会を作るために働くもの、という考えがあるからでしょうね。だから、儲け仕事に荷担するのはいけないことで、公共的な仕事が王道。でも、今の現実の社会の中で、資本主義経済は避けては通れないではないですか。だから、その中で何ができるのかということも大事ではないか、と反論したりして。でも失敗したら、ブランドは建築家に頼まなくなるだろうし、建築家の方もブランドの仕事はしなくなるでしょう。そんな責任を感じて、かなりドキドキしながら、最初の仕事をしました。
国谷
すごい。世界中のルイ?ヴィトンの店舗を設計されています。
青木
最初の仕事がなんとか成功したようで、以降、建築家がブランドのために設計することは普通のことになりました。そういう意味では、世の中のためになることが少しはできたんではないか、と自画自賛しています(笑)。
国谷
先生はおっしゃっていますよね。自分は内部のことから発想する建築家であると。ブランドの店舗というとどちらかというと外の見栄えに力をいれるんじゃないでしょうか?
青木
外装って、街からすれば街のインテリアなんです。だから、外装について考えることは、街の内部から考えることで、外装のあり方次第で、街を壊してしまうことも、街を良くしていくこともできるんです。
一番印象に残っているのが藝大だった
国谷
先生は藝大に来られたのが2019年で、まだ2年目ですね。
青木
はい、その年の4月はてんやわんやでした。同じ時に館長にもなったので。
国谷
すばらしいチャレンジです。ご出身は東京大学。藝大から声を掛けられた時はどう思われましたか?
青木
すごくうれしかったですよ。建築家って、独立した頃は仕事がなくて暇なんです。それでいろんな大学から設計の非常勤講師として喚ばれる。独立してからしばらくの間は、東京を中心とした関東圏のいろんな大学の講師をやりました。その中で一番印象に残っているのが藝大なんです。楽しかったんですよ。だから引き受けました。
国谷
楽しいとはどういうことですか?
青木
どう言ったらいいかな…。こちらが想像もしていない案を持ってきてくれることかな。今、大学の建築学科はたいてい工学部にあります。そういうところだと、だいたい想像の範囲内の案しか出てこないんです。正しい答えを論理的に導き出そうとするから、とっぴな案は出てきにくい。それじゃあ、僕は楽しくないです。
国谷
箭内先生(デザイン科教授)が、宿題を出すと45人から45通りの答えが返ってくるとおっしゃっていました。
青木
建築科は1学年15人なので、15通りの答えが返ってきます。設計には正解はないんです。それぞれがそれぞれなりの切実さをもって案を作ってくるのを、その課題にもっとも相応しいと思える非常勤講師を招いて、助手と一緒にぶつかるんです。終わるといつも疲労困憊ですが、刺激的で楽しいですね。建築科には9人の教員と9人の助手がいて、さらに非常勤の講師を喚んでいるので、学生数に対して、教える側はかなり多いと思います。
国谷
すばらしい! でも経営的にどうなのでしょうか(笑)。

青木
結果、いい建築家が生まれれば安いものです(笑)。何週もかけて、ひとつの課題に取り組みます。僕は「美術館を作る」という課題を3年生とやっていますが、毎週少しずつ異なる側面から美術館について考えてもらって、最後にその人なりの計画案にまとめてもらいます。教員側も皆、意見が違いますから、いろんな考えや感覚に出会えます。
国谷
それは楽しいですね。最高に面白いと思います。そんな場はなかなかないです、今。
青木
ないですよね。自分のアトリエでも同じようなことをやるわけですけど、仕事ですから、期限内に納得のいく案として完成させなくてはならない。だから、スタッフには厳しいことも言わなくちゃならない。「ここは違うんじゃない?」とか、その人自身の感性を越えたところで議論しなくちゃならない。でも大学はそんなプロとしての仕事を学生たちができるようになるまでをサポートする場所。うまくいかず悔しい思いをしたり、人に良さがわかってもらえず悶々とする経験を通して、学生たちは育っていくわけです。彼ら彼女らはじっさいに建物を作るわけじゃなく、案だけを何度も何度も作る。その練習を通してその人なりの基礎がいつの間にか築かれていく。大変だけど。
国谷
大変だと思います。真剣勝負ですね。
青木
真剣勝負。だから自分自身の仕事と両立できない、教員にはならない、とずっと考えてきました。自分のアトリエも4年で「卒業」してもらう仕組みなので、私設大学をやっている感じですし。でも60歳の還暦になった時、ここで人生がひとまわり終わったんだから、生まれ変わってまた0歳に戻って、今までならやらなかったことをあえてやってみようと思ったんです。それで、それまでだったらとうてい引き受けなかったことを、後先考えずに、えいや!で引き受けることにしました。それで、藝大の教員になり、美術館の館長になり…。
国谷
タイミングよく藝大からオファーがあったわけですね。
青木
藝大は67歳で定年なんです。となると最後まで働いても5年。まぁ5年だったら、仮に途中で辛くなってもなんとかやりおおせるかなと。建築でも5年間かかるプロジェクトはよくあることなので、これもひとつのプロジェクトとととらえればできるかなと。大学院のゼミには毎年数人入ってきます。ただ最初の年は、入試が僕の採用が決まる前だったからとっていない。最後の年も2年間の修士修了までみることができないのでとらない。だから、ゼミは3期までしかないんです。大学院としての活動はだから5年間のプロジェクトではなく、3年間のプロジェクト。そこでは「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」ということをしてみようとしています。

シン?マサキキネンカン??Ohmura Takahiro
僕たちの目の前にはいつも、僕たちと関わりなく既に空間があります。ゼロではない。その既にある空間をいじって、より居心地のよい空間にアップデートする。それが建築なんではないか、というのが僕の建築についての基本的考え方です。だからどんな建築も実はリノベーションなんです。広い意味で現実を変えるという。1年目は4人の学生が正木記念館をリノベーションしました。本当に変えてしまうのではなく、元に戻せるリノベーションです。2年目は学校の外で場所を借りて、そこを一時的にリノベーションしてもらおうと思っています。何か用途があってリノベーションをするのが普通ですが用途はなく、その意味で、純粋リノベーションです。
国谷
様々な空間をよりよい場所に変える、リノベーションするというのは、一から作るより難しいのではないでしょうか?
青木
ですね。そこにあるものをよく見て、よく感じて、それらと丁寧に対話を重ねていく。僕たちは、実はモノを見ているようで、見ていません。ちゃんと見えるようになるためには、ある種の努力と訓練が必要です。しかも変えると言っても、もともととまったく違うものにするのではなく、もともとのモノに隠れていた側面をうまく引き出そうとしています。さっき話題に出た馬見原橋は、橋を道にいったん戻して、そこから今の道で見えなくなってしまったものを引き出そうというプロジェクトですし、京都市京セラ美術館は、1933年に建てられた様式建築からそこに隠れていた魅力的な側面を発掘しようとするプロジェクトでした。学生たちに、そんな建築のあり方を体得してもらえたらな、と思います。
今まで知らなかった世界を作りたい
国谷
実は映画監督になりたかったそうですね。
青木
ええ、高校の頃、映画を作るか、小説を作るか、建築を作るか、そのどれかをしてみたいと思っていました。どれも、使うマテリアルは必ずしも新しくないけれど、その組み合わせ次第で、自分が今まで知らなかった世界を作りだせるところが共通していますね。映画だったら映像と音という素材、小説だったら言葉という素材、建築だったら建設資材という素材を使って、世界を作ります。ジャンルが違うので結果的にはまったく似ても似つかないものになるでしょうが、同じ世界を別々の形で作ってみることには、今も興味を覚えます。特に映画を作ることは生涯の夢ですね。
国谷
本屋さんで建築雑誌を見て建築家になろうと思ったと、とても簡単に決めたように書かれていますが、何かもっと建築家への志のようなものがあったのではないですか?
青木
いや、なかったです。中学の時に、学校の図書室でたまたまアントニオ?ガウディの建築の写真を見て、「すごい、建築って、こんな世界も作れるんだ!」って感動しました。でも、現実の東京は退屈な建築だらけでしょう。つまり退屈でない建築を作る余地はいっぱいある。だから建築家になるのは、3つの仕事の中でももっとも簡単。不遜にも、そう思い込んでしまいました(笑)。大学受験に落ちて自信をなくしたので、それで他の仕事は諦めて、建築に進もうと決めたんです。
国谷
理Iですよね。難しいですよ。
青木
高校時代、遊んでばかりで勉強していなかったので、浪人してはじめて真剣に勉強しました。だから進歩の余地が大きかったんでしょう、その勢いで受かったようなものです。東大は2年の後半に進路が決まるのですが、建築学科に進んで課題が始まって、「建築に進んでよかった。こんな楽しいものがあるのか!」と思いました。以来、「この楽しいことをずっと続けていたい」と思って生きてきました。
感覚から論理を導き出す
国谷
元々は芸術家志向が強かったけれど、もしかしたら通用しないかもとか、ここなら入れるかも知れないというプラスマイナスを考えて建築学科にいらっしゃった。でも結局は今、東京藝術大学の教授になって、今後の芸術家たちを育てている。いわば外の世界から来て、芸術一本槍でやってきたわけではない。その眼差しから見て、今の学生たちに一番教えたいこととか、こだわってほしいことは何ですか?
青木
東京藝術大学の建築科に入るためには、美術的才能とそれを磨く訓練がある程度は必要で、学科の成績だけならたぶん最難関ではないでしょう。だからなのか、ロジックが弱いというコンプレックスを持っている人が多いように感じます。
国谷
論理的に考えることとか。
青木
ええ、そういうのが弱いと思っている人が多い。でもそれは間違っていると思いますね。だって、論理で作られたものは正しいかもしれないけれど、たいていつまらないでしょう。もちろん、感覚だけ作られたものも深みはない。つまり、論理か感覚かという二項対立ではないんです。その両者がその一方が一方を支える関係になっている時に、いい建築ができるんじゃないかな、と思っています。で、論理から始まってそれを感覚に持ってくるのは、その逆の、感覚から始まってそれを論理に持ってくるより、ずっと難しいんです。だから、感覚から論理を導き出す努力をした方がいいのでは、と思います。
具体的には例えば、いくつか思いついたことから、あるひとつを選ぶとしますね。その時、そのままにしないで、なぜその案を自分は選んだのか考え、その感覚に対してできるかぎり嘘のない言葉を見つけます。言葉になると、感覚からちょっと距離ができます。論理っていうのは、そういう言葉のことです。で、言葉というのは、その上で思考ができる便利なツールなので、「だったら、こうしたらいいのでは?」というような、案を変えてしまうようなアイデアが出てくるかもしれません。でもそれで変えてみると、今度は、感覚が許さない。となると、言葉が間違ったのか、感覚が間違ったのか、そこで悩みますね。
国谷
自問自答ですね。
青木
自分の感覚に自信を持って、意識化を止めないで、その上でそれを怖くても捨ててみる。それを繰り返すことのできる体力を持てるといいなと思います。
国谷
先生は設計されている時に、相当、自問自答されているわけですか?
青木
自分だけではできないから、アトリエで一緒に設計している人たちに「これでいいんじゃない?」って聞くんですね。すると、「またまた~、冗談でしょう? ぜんぜんダメじゃん」って返ってくる。そう言われると腹が立つんだけど(笑)、それで議論になって、いつしか自分の感覚の方が変わって、今まで醜いと思っていた案が美しく見えてくる。僕が評価するのは、そういう時の相手になってくれる人たちです。自分の感覚は間違えているかもしれないって思うことが大切ですね。
国谷
学生との濃密なやり取りでは、むしろそういうところを引き出すというか、サウンディングボードのように、本人の考え方のいわば鏡になっていらっしゃる。

青木
どうしてこれがいいと思うのか、不思議なのを持ってくる人がいます。なんでそこにこだわってるの?って。でも、なぜこうなの?って聞いても答えが出てこない。そこを、「感覚は言葉にならない」じゃなく、感覚の近似値でいいから、ゆっくりでいいから言葉にする努力をすると、伸びると思いますね。
国谷
自分たちの土壌をデザインできる若い人がいっぱいいるとおっしゃいましたが、学生たちも領域を広げようとしているという感覚はありますか?
青木
ええ、それって、建築なの?っていうことをやる人がけっこういます。建築というものが確として先にあるのではなく、建築というものの領土を疑って、それを広げている。
国谷
それはすごく勇気付けられますね。
青木
藝大の建築科は、美術の一分野として建築を見ていて、かつ設計という実技が中心になっているところに、工学部にある建築学科とは違う特徴があります。だから設計ということと真剣に向き合えるところがいいですね。教員も大半が建築家で、多くが設計の実務に携わっている。でも皆、建築との付き合い方が違うから、講評会になると違うことを言う(笑)。前は、講評会で学生を差し置いて、教員同士で激論があったと聞きます。それも学生にとって、いい勉強になると思うので、そろそろ意識して、議論をふっかけてみようかな。
国谷
お忙しい中、こんなにたくさんお時間をいただいてありがとうございました。

【対談後記】
青木先生は、それまでいた建築事務所を辞めて独立した時、ちょうどバブル崩壊に遭遇してしまいます。まったく電話も鳴らず仕事が来なくて愕然となったそうです。
経済成長に行き詰まった社会からは、よりいいもの、新しいものを求める機運がなくなり始め、その後、2008年のリーマンショックで、本当にすべてが、いいものを目指すという方向を失ってしまった、と青木先生はお話になりました。
そうした建築家にとっての逆境をばねに、自らに課したのが「自分がデザインする土壌をデザインする」というチャレンジだったのではないでしょうか。建物の設計?デザインという枠を大きく超えて、「生きているところには空間、世界がある。その世界をもう少しいい状態にする、現実を変えるのが建築」と語る青木先生からは、様々な固定観念をこれからも変えていきたいという想いが伝わってきました。
【プロフィール】
青木淳
美術学部建築科/大学院美術研究科建築専攻教授
1956年神奈川県生まれ。東京大学工学部建築学修士修了。磯崎新アトリエ勤務を経て、1991年に独立し、青木淳建築計画事務所(現在はASに改組)を設立。
主な著書に『フラジャイル?コンセプト』 (建築?都市レビュー叢書 / NTT出版)、『JUN AOKI COMPLETE WORKS』(1?2?3巻 / LIXL出版)、『原っぱと遊園地』(1?2巻 / 王国社)、『青木淳 ノートブック』(平凡社)、編著に『建築文学傑作選』(講談社文芸文庫)などがある。
1999年及び2021年と2度、日本建築学会賞、2004年に芸術選奨文部科学大臣新人賞、2020年に毎日芸術賞を受賞。2019年4月より本学教授および京都市美術館(通称:京都市京セラ美術館)館長を務める。
撮影:新津保建秀
- 1
- 2