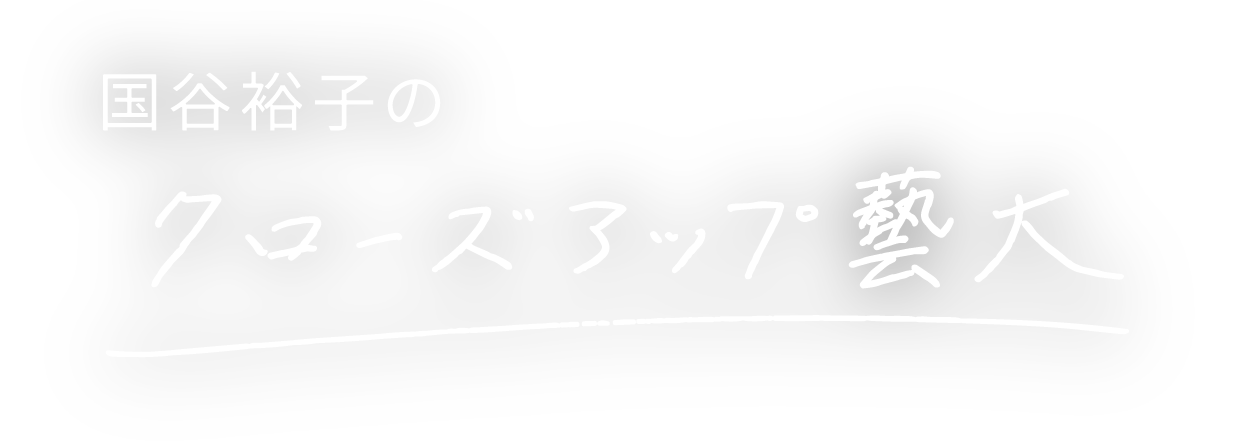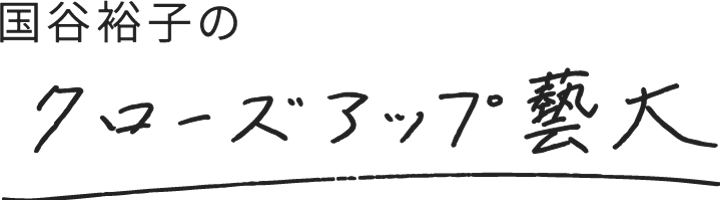第十九回 小林正人 美術学部教授
>>?前のページ
絵はどんどん進んでいく、言葉にならないところで
国谷
小林先生は藝大を卒業したあと佐谷画廊の佐谷周吾さんに見出されて、その後ベルギーのキュレーターであるヤン?フートさんにも出会い、今までいろんなチャンスを得て来られたと思います。お会いする前は、失礼ながら変わり者で破天荒というイメージが少しあったのですが、お話を伺っていると、自分がやりたいことに向けて何をすべきか非常に冷静に考えていらっしゃる。でも佐谷さんは、「彼はこのまま日本でやっていくのは難しい」と思って、外国に行くように言われました。やはり若い頃は、小林先生を受け入れるというか、絵を描く環境として日本は厳しかったのでしょうか。
小林
さっき言った藝大の卒業制作展の時にコレクターみたいな人が現れて、その人が展覧会をやらないかって言ってくれたんだよね。お金を出してくれて。その「絶対絵画」っていう展覧会の時に佐谷周吾が見に来て、それでその後、佐谷画廊でやるようになった。その時から国立にアトリエを借りてやり始めたんだけど、俺は絵を描けさえすればよくてさ。つまり展覧会をやろうとか有名になろうとか、そんな気持ちはこれっぽっちもなかったの。
国谷
それで生活していこうとは思っていなかったのですか?
小林
生活というか、絵以外のことはするつもりはなかった。絵を描き続けられればいいって、それが一番贅沢なんだけど。でもそう思ってて、それができていたから。カツカツだったけどね。だから学生たちに今言っていることは、俺だって最初からできてたわけじゃない。あの頃は何も考えてなかったよ。
国谷
とにかく絵が描きたかったのですね。

小林
絵だけ描いていたくて、それができてたんだよ、なぜか。
空の絵のイメージが頭の中にあって、もうほとんどできているんだって、友だちに話したんだ。あとは描くだけなんだ、描きたいんだよねって。そうしたら、その友だちが俺を国立の或るビルに連れて行って、そこに300号の2×3メートルのキャンバスが置いてあって、ここを使ってと言った。それでそこに住み始めて、佐谷画廊で展示をやるようになった。その国立のアトリエで、描いている時に具合が悪くなって救急車で病院に運ばれたんだけど、その時もその友だちが側にいて助けてくれたんだ。
救急隊に「看板描きが倒れてる」って言われたんだけど、空の絵は看板に近くてもいいと思っていたことも本当だった。その頃俺は、絵をせんせいに見てもらうことしか頭になかった。でも先生はバンクーバーにいるわけ。そうした時に、看板みたいなものが外にあったら、何かバンクーバーから見えるんじゃないかなって。佐谷画廊で展覧会をやることになった時も、せんせいに見に来てもらえるかもしれないって思った。
国谷
それぐらい世間知らずだった。
小林
そうそう、全く。自分の展覧会のオープニングだって行かなかった。時間が惜しいんだよ。ずっと絵を描いていたいから。だからひどかったよ。周吾が俺は日本ではやっては行けないと思ったというのは、そりゃそうだと思うよ。絵の問題だけじゃないんだよ。もしゲントに行っていなかったら、俺は国立で、いまだに空みたいな絵を描いていたかもしれない。だから全てがゲントに行ってからだよ。
俺は真剣だったんだけど、絵のことしかできなかった。頭の中に絵のイメージがどんどん生まれてきて、それを早く描かないと消えていっちゃうんだよ。だから話をしている場合じゃないんだよね。なんなら周吾も一緒に描いてくれというぐらい。だから周吾は大変だったと思うよ。金もかかるし。
国谷
そうですよね。ですからどうやって世界的に認められる画家になったのか不思議に思いました。国立の頃はキャリア形成について何も意識していなかったでしょう?
小林
うん、ゲントに行ってからかな、それは。だけど今だってさ、なんと言うか、藝大にすっぽり入ってはいないじゃないですか。
国谷
入っていないと思います。
小林
でしょう? でも俺は俺で真剣にやっている。LOVEゼミとか。
国立の頃は言葉とかそういうものは本当に大嫌いだったよ。絵のことを喋ったり言葉で書いたりとか。絵はどんどん進んでいく、しかも言葉にならないところで進んでいくから。今の学生たちは何でもかんでもまずコンセプトを言わされたり、言葉にできなきゃダメとか、かわいそうだと思うけどさ。国立の頃は、絵を言葉にしてその時間を止めるのは嫌だったからやらなかった。そういうのが総合的になっていくのはゲントに行ってから。やっぱり外でもまれないと。内だけじゃだめだな。それは藝大の学生に言いたい。
国谷
外に行ってほしいと。
小林
本当にそう。それと、自分探しは尊いように思われているけど、そんなことはないと思うよ。ただ自分を甘やかしているだけ。自分だって何だって、絶対的ものではない。やっぱり全てが相対的な関係で生まれてくる。外で揉まれることで自分もはっきりしてくるっていうか。だから、LOVEゼミでターゲットを決めてやることは自分を強化する。だけど、それと同時に、周りの世界に対して絵を位置付けることができていなかったら、やっぱり弱い。
気の持ちようで世界は変わる
国谷
『この星の絵の具』を読みますと、絵を描くきっかけとなった高校時代のせんせいや、イタリアで出会って一目惚れした今の奥様が登場して、小林先生はそういうはっきりとした人物の方を向いて絵を描いてきたように書かれています。一番好きな誰かに向けて自分の思いを描きながら表現するということが、やはり先生の原動力というか絵を描くパワーになっていますか?
小林
あるひとりの人をイメージして制作することを学生にやらせたのは、彼らはまだ自分の絵ができてないから。自分の絵を作るために色々とぐちゃぐちゃ悩んでるんだったら、ひとりターゲットを作ってやるのがいいだろうと思った。
この間の「あなたのアートを誰に見せますか?」という展覧会もそうだし、作家でも誰に見せるかっていうのはあると思う。だけど、今の俺にはそれはいない。もはやひとりの誰かとは言えないし、例えばセザンヌに見せたいとか、仮想敵じゃないけどそういうのを作り上げることもある。俺が「あなたのアートを誰に見せますか?」で展示した《画家の肖像》は、高いところにわざとストラクチャーを作って、それを感じてほしかったっていうか。
国谷
でも、恋をしていると世界が変わるとか、質感が立ってくるとか、イメージが湧いてくるとか、それが絵の力になるというようなことを書いていらっしゃいますが。
小林
死ぬほど苦しんでいる人とか、病気の人とか、そういう人も含めて、気の持ちようだと思うよ。全てが。それによって世界は変わる。だってそうじゃないですか。必ず死ぬんだから、どんな人だろうと。
絵を見る時だって、すごくうれしい時とかすごくつらい時とか、例えば歯が一本痛いだけで変わりますよ。つまり、人間はそういう生き物だし、だからすごく弱いところもあるし、強くなれるところもある。だけど、イメージする力は無限大。それをどれだけ引き出すか、そして何になるか。恋じゃくなくても何かうれしいことがあったら、例えば子どもが生まれてでもいいよね。その時の景色は絶対にいつも見てるものと変わっているはずだと、俺は思う。
ただの感覚のスイッチの問題なんだよね。これは難しい話でもなく、一瞬にしてできること。もう絶望的になっている人が0.01秒後に新しい世界に入ることが、絶対できると思うよ。そういうふうに世界を見ながら、そうなるように絵を制作すればいい。

国谷
作品の見方は人それぞれだけれども、見る人のイメージを喚起して、とにかくその人の中で質感が立ってほしいともおっしゃっています。
小林
そうそう、だからイメージの力ですよね。何かを見たり記録したりしたあとに、脳の中にある種の質感ができる。それが薄まっていったり、ぼやけることもあるけど、俺はその質感がチカチカ立ってくるように絵を作りたいんだよね。
国谷
小林先生は学生に、ターゲットに向かって描くということを強調される一方で、この絵でこの世界で何をしたいのか、絵によってこの世界とどう関係したいのか、絵で自分のいるこの世界をどう変えてみたいのか、そんな問いかけもされています。ターゲットに向かって描くということと、これらの問いかけの関係性がよくわかりません。
小林
ほとんどの学生は、自分が何をやっているかわかっていない。それは言葉にできなくたっていいんだけど、自分の感覚としてわかっているかどうかが重要であって。だから周りの世界を想像することだよね。
この《画家の肖像》だって、ウクライナで描くのと日本で描くのとでは絵の意味が変わってくる。絵の中の世界だけでやっていればきれいだよ。ヴィトゲンシュタインが言う「ツルツルの氷の世界」ってやつだ。だけどその外にはザラザラの世界があるわけで、それによって中も影響を受けたりして変わってくる。だからコンテクストが変わって生まれ変わったりして絵画は続いているんだよね。
だからそういうものに対応できるような絵を作っていくための第1歩として、まず好きな人に向けて描いたらいいんじゃないかな。そしてその絵は実際にその好きな人に渡して、その好きな人にどんな空間にかけてほしいか想像する。この絵があることで、この世界に対して自分が何をやってるのかをわかっていくというか。だから絵を描くってことは、何かひとつのことじゃないですよ、やっぱり。
「この星の」という感覚のスイッチ
国谷
作品を制作する上で、いろんな社会的な枠もあるしキュレーションの事情という枠もあります。小林先生にとって、芸術家としての自由と、絵を描く時の制作上の自由は全く別物なのかなと、お話を聞きながら思ったのですが。
小林
それを意識して分けていないけどね。というか、一言で言えば、芸術家から自由を取ったら何も残らないと思ってるよ。俺が最初から四角い平面があったらダメだって言うと、壁画とかそういうのをやればいいじゃないですかとか言う人がいた。だけど、俺からしたらそっちの方がよっぽど不自由でさ。動きはきかないし、どこからどこまでって決まってるし、壁だって限界はあるわけよ。だから「この星の」という感覚が生まれた。絵はモノとしてはこのサイズだけど、必ず展示なり、どこかに置かれるわけですよ。そうした時に空間が生まれる。この絵の支配する空間というか、必要な空間はどこまでなんだという話になった時に、どこで切ろうが別にOKなんだという感覚が生まれたの。
つまり、どこを切り取っても「この星の」景色で、この部屋で見たっていいし、この廊下も入れたっていいし、でっかい建物の中にこの絵があるって見方をしてもいい。限界を定めるのはつまんないから、どこで切ってもOKになる方法として「この星の」という感覚が生まれた。だからそれは、ただの感覚のスイッチ。

国谷
その感覚を得た視点の広がりというのは素晴らしい。
小林
あれでやっぱり自由になったかな。
国谷
小林先生は「武器は想像力である」とおっしゃっています。果てしなく広がる世界をどのように切り取ったらいいのか、どこまでを引き受けられるかというのは、素晴らしい感覚だなと思います。
小林
絵の中に美しい完璧な世界を作りたいんだったら、俺は絵の中だけでやってるよね。それはどこに持って行こうがどんな空間に置こうが関係なく。でも俺の場合はそうやって、枠も自分で作りながらやっていく。
ゲントの馬小屋ででっかい絵を描いてた時に、俺は外でタバコを吸ってたんだけど、小屋の中に黒猫がトコトコトコって入って行って、しばらくして、ここ(鼻)に黄色い絵の具をつけて出てきたんだよね。それを見た時に、あ、床置きにすると何でもくっつくんだなと。それが現実で、俺はそれをどこまで引き受けるのかということを初めて考え出したのかな、その時に。壁に上げればくっつかないんだよ、とりあえずは。だけど床置きにしてたらくっつくんだよね。藁だってなんだっていろんなものが。だからそれを絵の中に一緒に取り込んで、それでどこまで自由にやれるかという。
ストラクチャーが変わらなければいけない
国谷
小林先生が自由について深く考えてらっしゃる一方で、世間はどんどん色々なものをカテゴライズし始めています。世界中で、人々がコミュニケーションする上でも分断が広がっています。例えばSNS上のこの人たちとは仲良くできるけど、他の人とは交じわらないとか、固定観念で人を捉えてレッテルを貼ったりとか、カテゴライズがどんどん細分化されています。世界は果てしなく広がってつながっているのに、社会は逆の方向に動きが加速しているように感じてならない。

小林
そう思うけど、でも本当は未来のことを考えたら、そういう切り取り方をしていく人はAIに代わられちゃうよね、きっと。だから、社会のどこかで変なことを考えているやつが何をどう動かそうとしているのか知らないけど、やっぱり矛盾する相反する両方の方向に行くはずなんだよね。「そうじゃないんだ、だから空を見なきゃいけないんだ」とか、そういう思考は間違いなく必要になってくる時代のはずなんだよね、これから。
国谷
人はわかりやすい方が安心するし、何でも早く分かりたい。情報が消費されるスピードもペースも速まっている一方で、小林先生が今おっしゃったように、だから、もっと空を見ないといけないとか、そういったことに人はどうしたら気づくことができるのでしょうか。
小林
国谷さんは藝大に来て、やっぱりいろいろなことに気づくじゃないですか。俺は学生に驚いたって言ったけど、大学自体にも驚いたんだよ。冗談抜きで問題だらけで。ストラクチャーがやっぱり本当に固すぎるんだよ。それぞれが村みたいな感じで。
国谷
縦割りで、蛸壺みたいな。
小林
だからさっきの枠の話じゃないけれど、ある意味枠が上手くで
国谷
よく藝大で教えることを引き受けましたね(笑)。
小林
ただ、俺は学生と一緒にやるのは好きなんだよ。ここで制作しながら小林研の学生たちを見たりしながらさ。
もうひとりの自分がいるから自由にできる
国谷
小林先生の制作方法は、木枠にキャンバスを張りながら同時に描き進めるというものです。絵の中に入り込むようにキャンバスに近づいて、手で直接描くのですが、先生は描いている時にどこを見ているのでしょうか?
小林
キャンバスに近づいて描いている自分は直感的にやっていて、離れたところからこの絵を俯瞰して見ているもうひとりの自分がいる。そこからの指示が瞬時に入ってきて、だから俺はここで自由にできるわけ。もうひとりの自分がいなかったら少しも自由ではなくて、自分の中を堂々巡りするだけだと思う。

だけどそれがわかったのは後付けっていうか、言葉にしてなくてね。2000年に宮城県美術館で個展をやって、長谷川祐子さんとヤン?フートと対談した時にそういう話になった。「小林さんはどこを見て制作しているんでしょうか?」って。キャンバスとの距離がゼロの時に、今やろうとしているここ(キャンバスとの接点)を見ていないことはわかるんだよ。それはもう手でできる。じゃあ次にやろうとしているところを見ているかっていうと、それも手でできる。だからやっぱりわかんないなって。だけど、木枠と絵具とキャンバスっていう3つのものを自分が自由に操っていて、それがうまくいっているかわからない状態で、つまりそれを意識しないでやりたいわけ。
国谷
いちいち意識したくないのですね。
小林
子どもの頃、柵を意識しないで遊びたかったようにね。言葉では言えないんだけど、マニュアルでジャンボジェットを操縦しているような感覚になるんだ。
手って、ある意味高度なんだよ。道具としてものすごく精密。手がプリミティブで筆を使ったら文明的なんてことは全くない。大昔から人間は手を精密な道具として使ってきたから。情感がプリミティブなだけではない。それと同時に、俺の自由な描き方だと、平らじゃないところに描くのは、筆だけでやってたらポロポロはがれていくよ。後ろから支えたりしていくから強くなっていく。そういういろいろな物理的な条件とかも含めての自由なんだ。
国谷
最初から絵筆を使わず、手で描いていたのですか?
小林
いや、それができるようになったのは《絵画の子》(1994年)ぐらいからで、《絵画=空》(1985-1986年)を描いている時は張りながら描くところまでは行ってなかった。頭の中にある本当に完璧に美しい空と、目の前の300号のキャンバスと絵具のチューブがなかなか一致しなくて、この空をどうやってそこに描くのかって、1年以上かけて試行錯誤して作ったよ。それはもう本当に若い時にしかできない、ばかばかしいくらいの純粋さというかさ。
世界は矛盾に満ちている
国谷
小林先生は制作について表現する時、よく「遅い」という言葉を使われます。「ある平面の上に描くのでは遅い」、「白いキャンバスの前に立って描くのでは遅い」、「仕上げを入れたら遅い」など。他にも「できた瞬間に止める」「作り過ぎない」とか。
小林
多分、モノとの格闘なんだと思う。(目の前のコーヒーカップを手に取って)例えば、コーヒーの入ったコップを作りなさいと言われたら、既に存在しているコップにコーヒーを注ぐんじゃ遅いと思うわけ。ひとつにならないっていうか。じゃあどうするかというと、コーヒーになるものの始まりの段階と、コップになるその原子の段階から、それをバーっとミックスして、モノが出来た時にはコップにコーヒーがすでに入っているという状態を作ろうとする。つまりコップというものがあって、そこに新たにモノを付け加えていくのは俺には汚く見えるんだよ。だからモノを減らしていきたいわけ。イデアル(理想的)にはね。わかります?

国谷
わからないです(笑)。モノを減らしていきたいから、すでに張ってあるキャンバスに描くのでは遅いのですか?
小林
あのね、俺が藝大に入って絵を始めた頃は、「絵画は終わった」って言われてた時代なんだよね。アメリカのフォーマリズム、モダニズム全盛の時代で、絵というのは四角い平面で、そこには中も裏もない。その四角い平面から逆算して割り出されて、最終的にその四角い平面に合致するものしか描いてはいけないみたいな。だから演繹的なもので、俺の言葉で言うと、枠がある。その枠に合致する、演繹的にそこに矛盾をきたさないものしか描いてはいけない。つまり、イメージを描けるわけがない。そういう時代だった。
で、俺は子どもの頃から枠みたいなものが嫌いだった。絵で言えば、最初に四角い紙があってそこに描くのは嫌で、描いていたものが始まりじゃないと嫌だった。原っぱに柵があって、その柵から絶対に出ちゃいけませんと言われてそこに入れられたら、俺は遊べない。まずその柵から何とかして出ようとすると思う。
絵を描くとか何かを作る時は、やっぱり枠が最終的に必要だよね。それがなかったら、モノとして成り立たない。だから、最終的には枠が必要なんだけど、内側が、つまり中で自由にできる枠でないと嫌だということ。だから最初は形もないし平面でもない。木枠も四角ではない。絵の具と木枠とキャンバスという3つのものを同時に進行させながら最終的にひとつの作品にする。それが俺の「自由について」。自由について言えることなんてほとんどないけど、言えるとしたら、俺がどう枠を作っているかということぐらいなんだ。何をどう描こうか画家の自由なんだけど、やっぱり枠が絡んでくるから、不自由になったり、色々な制約が生まれてくる。だからそれとどうディールしていくかなんだ。
お前は誰なんだ? 何をするんだ?
国谷
最後に、短く言うのは難しいと思いますけれど、学生たちに一番伝えたいことは何でしょうか?
小林
明日のために虎視眈々と牙を磨け!と。一言で言えば。自分の絵を描きたいんだったら、そんなのは学校を出た後にいくらだって時間がある。それを続けられる力をつけるために学ばないといけないと思う。
俺が藝大に入った時は、俺なんて今の学生の足元にも及ばないぐらい何も知らなかった。青木繁とか佐伯祐三とか、そういうのに多少憧れているぐらいで。入学してから、俺の背中みたいなところに自分が知らなかった“歴史”が現れたんだよ。それまでは歴史とか考えたこともなくて、親はいたけど自分だけが生きてるって感じでさ。だけど、歴史が背中に現れて、時代を遡って過去から現在へと長い道が繋がったんだよ。美術の歴史だけじゃなくて、人類史的な感じかな。その最後にはクロマニヨン人の洞窟まで出てきて、そこまで行った時に背中をドン!と押されるような感じがして、その時初めて俺の中に“自意識”が生まれた。「お前は誰なんだ、何をするんだ? 絵を描くとか言ってるけど、何を描くのか、何のために絵を描くのか?」そういう自意識だよ。だから俺は歴史を勉強することは大切だったと思う。でも、それは座学とかそういう次元じゃなくて。多分どんなジャンルでも歴史を知らなかったら、今、自分がどこに立っているかわからないわけよ。それは何をする場合でも必要なんじゃないかな。
要は何だっていいんだよね。自分が今どこに立っているか、何をするんだということがわかる何かならば。つまりそれによって、どれだけ好きになるかということなので。好きになって夢中でやっているやつに勝てる奴はいないって! どんな場合でも。

【対談後記】
小林先生との対話はあっという間に2時間を超えました。
印象的だったのは自分の考え方や想いを伝えようとする先生のとても一生懸命な人柄と、その佇まいです。言葉を重ねながら時折、「言っていることわかりますか」と私に尋ね、「わかりません」と答えるとまた熱心に身振りを交えながら話してくれます。アトリエに置かれていた馬の姿をした自画像の持つエネルギーに圧倒されましたが、作品だけでなく先生の伝えようとする言葉の熱量にも引き込まれてしまいました。
個展の会場であの馬の姿をした自画像がどのように見えるのか楽しみです。

【プロフィール】
小林 正人
美術学部 絵画科油画専攻 教授
1957年東京生まれ。東京藝術大学美術学部油画専攻卒業。
1996年サンパウロビエンナーレ日本代表。1997年ヤン?フート氏に招かれ渡欧、以降ベルギー?ゲント市を拠点に各地で現地制作を行う。2006年に帰国、福山市?鞆の浦を拠点に制作を続ける。2010年より東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻准教授、2017年より現職。主な個展に「自由について」シュウゴアーツ(東京、2023)、「この星の家族」シュウゴアーツ(東京、2021)、「画家とモデル」シュウゴアーツ(東京、2019)、「ART TODAY 2012 弁明の絵画と小林正人」セゾン現代美術館(長野、2012)、「この星の絵の具」高梁市成羽美術館(岡山、2009)、「STARRY PAINT」テンスタ?コンストハル(スウェーデン、2004)、「A Son of Painting」S.M.A.K(ゲント、2001)、「小林正人展」宮城県美術館(宮城、2000)など。著作に『この星の絵の具[上]? 橋?学の?の下で』(アートダイバー、2018)、『この星の絵の具[中]ダーフハース通り52』(アートダイバー、2020)。
撮影:縣健司
- 1
- 2