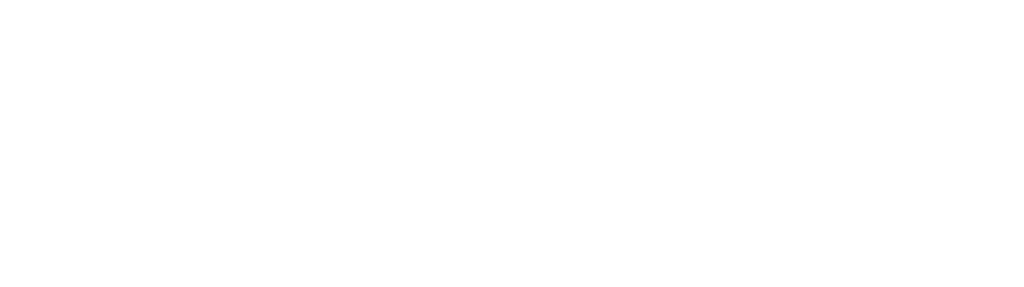- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第十一回 保科豊巳「藝大での80年学生時代の現代美術の自由と苦悩」
私は、今年1月の退官展「萃点SUI-TEN」の展示の準備のため久しぶりに倉庫に所蔵していた過去の作品を調査していると思いがけず、ずっと忘れかけていた博士入学時の作品を発見したのです。この作品がきっかけとなってこの頃の学生時代の苦渋の思い出が一気に湧き上がってきました。もちろんこの作品は退官展に展示することにしました。これは1981年の博士入試のために製作した藝大のコンクリート壁を剥がした「共律」というタイトルの作品でした。
私は油絵科に1975年に入学、当時70年代の激しい学園紛争が下火を迎えていた頃でした。
油画では入学試験が40倍という難関の受験でした。現在の入試に比べ、より長期にわたる入試日程で実施され最後の受験科目の終わった頃にはもう生も根も尽きて倒れてしまったことを覚えています。1次、2次、そしてなんと最終試験は学科試験だったのです。難関を突破し最初の授業が古美術研究旅行でした。春の古都への旅は長い受験勉強の疲れを癒してくれました、特に奈良の古寺巡りの里の長閑な風景は一層記憶に残る旅でした。その他の1年生のカリキュラムは年間に2課題のみで、学生は1ヶ月から2ヶ月かけて1課題を仕上げるといったゆっくりした制作時間で進められ芸術の道に進む自分を自問するような課題でした。最初の課題は自分たちでゴミを拾ってきてアトリエ内に盛り上げて描くといったもので自主課題でした。2年生以降は人物ヌード課題で人体を中心とした制作課題でした。卒業制作では提出作品は100号の油画作品提出と決められていて決して他の素材での提出作品は許されませんでした。
私は3年生ごろになると大学外でのアートシーンに目が向くようになりよく神田や銀座のギャラリーを見て回って歩くようになりました。その過激で逸脱した美術の手法に驚嘆と憧れを持って引き込まれて行きました。現代美術が時代を先取りしていたのです。そこは70年代「もの派」の世代の活躍している頃であり、ヨーロッパ、アメリカの現代の美術状況が日本の若い芸術家の世代に強い影響を与え、逆に「もの派」はこれに対抗するように日本独自の現代美術表現を産み出していました。また新しい時代の美術批評家も生まれていました。東京藝術大学では、私達は当時芸術学科の実技の講師で藝大に教えにきていた榎倉康二を知ることとなり、パリ青年ビエンナーレや、ベネチアビエンナーレに出品して活躍していた彼ら「もの派」と言われた芸術家達に強烈な影響を受けました。
私たちが大学院に入る頃の藝大での現代美術への動きは、現代美術の常勤教員としては杉全直教授が就任してきたことから始まりました。彼は僅か3年間の勤務でしたが現代美術のゼミを指導してくださり、その杉全直教授の後任として榎倉康二教授が常勤として就任したのです。私は木版画の野田哲也教授の研究室にお世話になり日本表現としての現代美術を志向していくのですが、アカデミックな藝大の絵画科の中も少しずつ現代美術の表現が許されるようにはなったとは
藝大にも博士課程ができることになって私の学年ではこれをめぐって議論されました。芸術家に博士とは何か? とりあえず卒業してもアトリエも無いので芸術家になるための猶予期間ということで先生たちも了解し、学位は取得しない、つまり受験者は博士号を取らないという条件で合格を許されたのでした。入学試験も劇的でした。この時受験した私達4名の現代美術学生は油画の表現に反すると言うことでほぼ絶望的な状況にあって半ば諦めていました。壁を剥ぎ取る保科、水をホースに流す田中、フェルトを丸めて立てかける川俣、佐川はミニマルな抽象平面、といった作品表現です。とても認められるような作品ではなかったのです。近代の諸問題に対抗する芸術運動が主流であった世界のアートシーンに対して藝大では近代そのものだったからです。話すと長くなりますがこの時、重病で体調を崩されて千駄木の日本医科大学に入院されていた杉全直先生はこの審査のためにわざわざ病院から抜け出して審査会の途中から出席してくれたのです。ほとんどの教授が認めなかった私たちの作品を杉全直先生は強く援護し審査をひっくり返したと後で聞かされました。
博士に合格した我々は、自由を求め自由な制作環境を創るため各自4人の大学院のアトリエを解放して演習室と名付け、誰でも使える自由な展示室としたのです。これは現在でも残っている油画の演習室の始まりです。ここで私たち学生は自主ゼミを開講し展覧会も毎週企画したのです。このことは当時の「美術手帖」でも取り上げられ評判となりました。私達はその2年後、川俣がベネチアビエンナーレに出品、私がパリ青年ビエンナーレ出品することとなりました。学生作家の誕生でもありました。藝大は少しずつ開かれていって、後輩も国際的な芸術家が育っていくようになっていきました。今では藝大において当たり前のように自由に制作活動が行われている現代美術表現もその時代にはプレッシャーとの緊張感の中で作品を生み出す決死の思いがありました。またこの緊張感が藝大生であるといったアイディンティティーを生み出していたように感じました。思い返せば、当時の私たちには藝大の中においてさえも学生というよりも芸術家の仕事をしているんだという気構えが学生同士の中にあったように思い出されます。
今を見ると、社会現象として問題にされている、マルクス?ガブリエルの言う自由の暴走、欲望と幻想が入り混じった現代社会の意識の反映を今の学生はどのように思うのだろうか?
写真:古美術研究旅行1975年 山川輝夫教授(右上から7番目)、田口安男教授(左下から2番目)と。同級生中央下が筆者。室生寺にて
【プロフィール】
保科豊巳
美術学部絵画科教授
1953年 長野県生まれ
1981年 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻 版画 修了
1984年 東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻 単位修得退学
2002?03年 文部科学省在外研究員として渡米
1980年、自身の故郷の池で行ったパフォーマンス《氷上の痕跡 池の上でのイベントを発表。1982年に第12回パリビエンナーレにて《間「木、紙、墨」》を発表以来、国内外にて日本の素材?思想を題材にした多くの作品を発表している。1995年より作家活動と並行して東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻にて25年に亘り多くの学生を指導してきた。