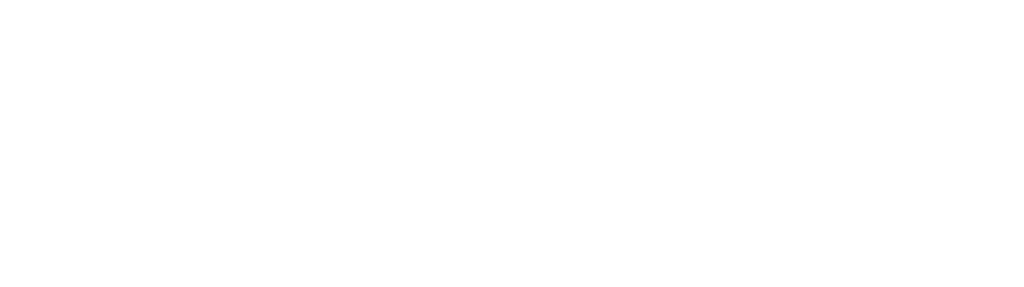- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第二十二回 桐山孝司「メディア映像専攻特別演習2020」
大学院映像研究科メディア映像専攻には、前期に特別演習(通称、特演)という一連の科目があり、5人の教員が2週間ずつ計10週間続けて行う。例年、修士1年は4月に入学してすぐこの特演に突入し、日々課題に取り組む。体力も使うので、7月に入る頃には気のせいか顔が細くなっている人もいる。しかしアイディアを映像にすることについては、4月の時とは段違いに力強くなっている。ちなみに大学院を出て何年経っても、特演という言葉はまだ独特の響きを持っているようである。
その特演について、2020年度前期は全てが遠隔授業となったため、まず教員の方がどうしたものかと思った。実技科目なので試行錯誤が欠かせないが、その様子を遠隔でしか見ることができない。自宅でこなせるのか、課題は例年と同じでよいのか、機材は何を渡せばよいかなど、心配は多かった。しかし全員にiPad Proとソフトバンク株式会社様よりご提供を受けたモバイルWi
特演では課題として何を出すかが重要である。最初に担当した畠山直哉教授は、例年だとカメラ?オブスクラを作り、自分の手で像を定着させる課題を出している。カメラ?オブスクラとはごく小さい穴を通って差し込んだ外光が暗室の壁に像を結ぶことだが、今年はステイ?ホームならぬ”Being Distant, Staying in CAMERA”、つまり自分自身が部屋の中にいて像を捉えるという課題になった(カメラはもともと部屋を意味する)。実際、部屋の中でいろいろな方法で映像が捉えられていたので、この課題の意図はうまく伝わっていたと思う。
佐藤雅彦教授の出した課題の1つ「2つの画面の間に在るもの」では、二人一組で2画面からなる映像を作った。今年の状況では、グループで取り組む課題はチャレンジングだったと思う。まだ一度も直接顔を合わせたことがない人たちであり、果たしてグループワークができるのか、課題を出す側も不安である。しかし蓋を開けてみると、同じ場所にいては望めないような、リモートであることを利点にしたアイディアもあった。山岸耕輔と松井靖果の「海響」では、それぞれ日本海と太平洋に向かって立つ2人が2つの画面の中で同じように手を上げ下げする。すると同じように波の音が大きくなったり小さくなったりする。この同期が一体どれだけ離れた場所で起きているのかを意識すると、自然とその間に横たわる日本列島の大きさが感じられる。
高山明教授は「家庭用ツアー?パフォーマンスの作品化」として、移す、遷す、写す、映す、感染すなど複数の意味でのうつすことを課題にした。これに答えて孫奎星は、中国でステイ?ホームになっている複数の知り合いに依頼してパフォーマンスをした様子を撮ってもらい、それを使って時間や場所を移動する映像にした。その次の2週間は私が担当して「シミュレーション、ゲーム」を課題にしたのだが、彼はさらに映像のオンライン展示の一方法としてパフォーマーに自分の部屋の3Dスキャンをしてもらい、この部屋に住む人が行ったパフォーマンスと分かるように部屋の壁に映像を組み込んだ。こういった距離を超えたデータのやりとりによって制作をするのも、遠隔での作業が自然になった今ならではの展開だと思う。
現在、特演は最後の桂英史教授の回に入り、身体と映像、およびオブジェとしての本の課題に取り組んでいる。これらの成果は9月にオンラインで開催するOPEN STUDIO 2020で公開する予定である。
 ?
?
(東京藝術大学 元町中華街校舎の研究室)
【プロフィール】
桐山孝司
東京藝術大学大学院映像研究科 研究科長 メディア映像専攻教授
東京大学大学院工学系研究科修了、工学博士(1991)。東京大学人工物工学研究センター、スタンフォード大学設計研究センターなどを経て現職。設計の知能化を出発点として、知識情報処理、インタラクティブメディア、映像メディア学などの分野で研究を行ってきた。EUCLID(佐藤雅彦+桐山孝司)として「計算の庭」(2007)、「指紋の池」(2010)、「統治の丘」(2015)などの作品を発表している。