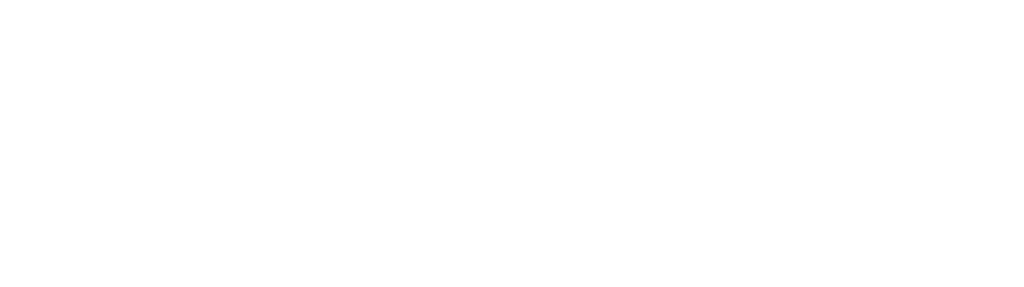- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第二十四回 杉本和寛「新型コロナに踊らされながら」
この4月から5月にかけて、緊急事態宣言下ではあったが、所用のため大学構内に足を踏み入れることが何度かあった。学生が構内に立ち入ることができないのは入試期間中も同じことであるが、明らかにそれとは質感の異なる静寂と、桜の季節から若葉の季節に移り変わろうとする外の温度感との落差が、人気のない校舎をまるで廃墟のように感じさせた。学生のいない大学というものが、生命感を失った身動きのできない巨人のように見えたものである。
自分の研究室に辿り着いて、たまたま(あるいは意識的に)手にしたのが、上にその挿絵を載せた『安政風聞集』である。これは安政3年(1855)に江戸を襲った大風災を扱うルポルタージュで、後に『安愚楽鍋』などで知られることになる仮名垣魯文が手がけており、江戸各地の大風や洪水による被害が色刷りの挿絵も交えて詳細に報告されている。既にさまざまな記事や書籍で言及されていることだが、江戸末期にあたる安政の時代は次々と災異が訪れ、江戸という土地に限っても、安政2年の大地震、翌3年のこの大風災、4年にはインフルエンザ、5年にはコレラの大流行など、嘉永6年(1853)にペリーの黒船来航があったこととあわせると、まさに物情騒然たるありさまだったのである。
断続的にみられる地震による被害や、昨年度からの台風による風水害、新型コロナウイルス、さらには7月の豪雨被害などを並べていくと、何やら160年余り前の混乱や困窮に重なり合うところも少なくない。そうした被害の情報がさまざまな出版物―書物?錦絵?一枚刷など―を通じて人々に提供されるようになったことは、この時代の大きな特徴であるとともに、新聞?テレビ?ネット等で情報が垂れ流されている現代の先駆ともなっている。安政頃の江戸の人たちは、出版物に示された克明な被害の数字やショッキングな絵柄に驚き、不安を募らせ、それと同時にある種の安堵も得たことだろう。また、SNSこそなかったとはいえ、それに類する流言飛語や噂話は江戸時代の人々「お得意」のものであり、陸続と出現する「感染症の専門家」ならぬ怪しげな宗教家もどきや祈祷師なども、そうした不安を煽ったに違いない。科学そのものやメディアのツールは大きな進歩や変化を遂げたとはいえ、そこから得られる情報についつい踊らされてしまうのは、百数十年前も現代も同じことで、我々人間の心理そのものは、なかなか進歩も変化もしづらいようである。
まずは遠隔授業でスタートするという世界的な流れに沿って、藝大も5月11日から授業を開始した。つい数ヶ月前までは想像もしなかった形態での授業が、さまざまな問題点を抱え批判を受けながらも、何とか夏休みを迎えるこの時期まで辿り着けたのは、このコラムを担当された桐山先生や亀川先生らの奮闘の下、学生?職員?教員がこの非常事態に対して多くの不安や不満を押し殺しつつ対応し、努力してきた結果である。6月からは音楽学部でも少人数でのレッスンを開始する専攻もあらわれ、7月になると学生の姿を目にし、話し声を耳にする機会が出てきた。昼食を食べた後なのか、マスクもせずに近距離でおしゃべりに夢中になっていたり、久しぶりに会った友達とハグしている姿をみると、「おいおい、大丈夫か?」と思ってしまうが、これも廃墟に生命が戻りつつある過渡として、十分な注意をしつつ受け入れるしかあるまい。
後期からは学部全体でレッスンの枠も拡大し、学生がキャンパスにやってくる機会も大きく増える予定である。ともかく学生たちのためにできることを一つずつ実現していくしかない、と腹を括って対応したいところであるが、このところの新規陽性者数の大幅増加と医療機関の逼迫という情報の氾濫に、またまた不透明な先行きへの不安を煽られてしまう自分がいる。『安政風聞集』末尾に、『孔子家語』から「所謂災妖は善政に不勝(かたず)」を引用し、無事に大風の静まったことを告げているが如く、感染症を封じ込めることはできないまでも、この国の「善政」がたしかな道筋を示してくれるとありがたいものである。
写真(上)『安政風聞集』巻之中「大洪水の挿絵」
【プロフィール】
杉本和寛
東京藝術大学音楽学部長 言語芸術?音楽文芸教授
東京大学大学院人文社会系研究科(国文学研究室)助手を経て、1999年から音楽学部講師、2000年同助教授、2010年から同教授。
専門は日本近世文学で、特に西鶴や浮世草子など17世紀後半から18世紀前半の散文作品。
共編著に、『八文字屋本全集』(汲古書院)、『西沢一風全集』(同)、『西鶴と浮世草子研究 Vol.3』(笠間書院)、『浮世草子大事典』(同)、『〈奇〉と〈妙〉の江戸文学事典』(文学通信)、『文化としての日本のうた』(東洋館出版社)など。