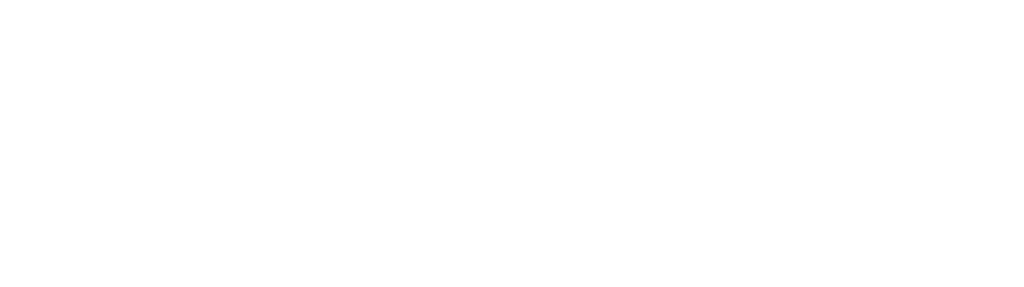- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第三十三回 藤崎圭一郎「『藝える』の現場から」
2017年から本学の広報誌の編集長を務めている。それまで本学には『藝大通信』という広報誌があったが、当時副学長だった故?松下功先生から、雑誌名も含めて全面的にリニューアルしたいから手伝ってくれと言われて、ハイかYESのどちらかしか言えない雰囲気もあり、「やらせていただきます」とニコニコ顔で返事をした。
松下功先生が「編集委員会をつくらないでいいから、好きなようにやってくれ」と言っていただいたのが本当に有り難かった。私は “現場主義者” なので、現場に行って肌で感じたことをいかに誌面に反映させるかが最も大切だと信じている。いちいち事前に企画を出して、取材現場に行ったことのない複数の教員で構成される会議に諮っていたのでは、生きのいい記事や尖った企画などできなくなってしまう。
デザインは、以前からいっしょに仕事をしたいと思っていた本学デザイン科出身の有山達也さんにお願いした。有山さんも徹底した現場主義者だ。有山さんは出来る限り取材に同行してくれる。編集企画にも最初の案出しの段階から参加してくれる。「藝(う)える」という印象的な雑誌名の名付け親も有山さんである。編集は小林沙友里さん。段取り上手の彼女がいないとこの雑誌は回らない。
「読ませる雑誌」というのが『藝える』のコンセプトである。もらったはいいけど、パラパラッとめくっただけで机の上に積んでおき、そのあと二度と開かれないまま古紙回収に、という運命をたどる広報誌にはしたくないという思いがあった。愛情と好奇心をもって、この外からはかなり見えにくい芸術の学び舎の内情を優しき言葉で伝えてくれる大谷道子さんらライター陣には深く感謝をしている。私は今も雑誌ライターの仕事をやっているが、大谷さんの原稿には毎回「私には、こうは上手くまとめられないな」と嫉妬に駆られてしまう。
さて、12月発行予定の第7号だが、特集タイトルは「コロナ禍だろうが、芸術がないと生きていけない」。今年度前期はほとんどの授業がオンライン授業となり、後期になって実技を中心に対面授業が再開されたとはいえ、さまざまな活動が制限されるなかで、教員や学生たちがどうこの状況に対応していったのかをレポートする。教員間の遠隔授業のノウハウ共有に多大な努力をしてくれたオンライン授業ワーキンググループ取り組みを、メンバーである岡本美津子先生、亀川徹先生、桐山孝司先生、八谷和彦先生の座談会で振り返る。
しかし、今号の主役は学生である。初めて学生編集委員を募集して、学長と座談会に参加してもらったり、1年生がどうコロナ禍を過ごしたかをテーマにした記事をつくってもらったりしている。コロナ禍で大学の施設の使用が制限され、展覧会や演奏会などが中止や規模縮小に追い込まれようとも、学生の学びへの意欲は減ずることなく、むしろこの危機を跳ね返すくらいの強い意思をもって、学?たちが芸術の実践と研究に向き合ってきたことを伝えたいと考えている。
『藝える』のバックナンバーは、下記のアドレスからPDFでダウンロードできる。しかし、できれば冊子の状態で『藝える』を読んでいただきたい。配布場所や郵送申し込み方法もこのページに記載されている。表紙は活版印刷。ページをめくるリズムに合わせた写真と読み物の配置──そんなことにまで細かくこだわった雑誌を手で触れて味わってほしい。

(2020年10月23日 12月発行予定の『藝える』7号のために行った学長と学生との座談会の様子)
写真(上):『藝える』6号表紙。現在配布中。藝えるは植えると同義。
?
【プロフィール】
藤崎圭一郎
東京藝術大学美術学部デザイン科 教授
1986年、上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業。同年、株式会社美術出版社に入社し、90年4月?92年12月に『デザインの現場』編集長を務める。その後フリーランスのデザインジャーナリスト、編集者として独立。金沢美術工芸大学、法政大学などの非常勤講師を経て、2010年、東京藝術大学美術学部准教授。2016年より現職。