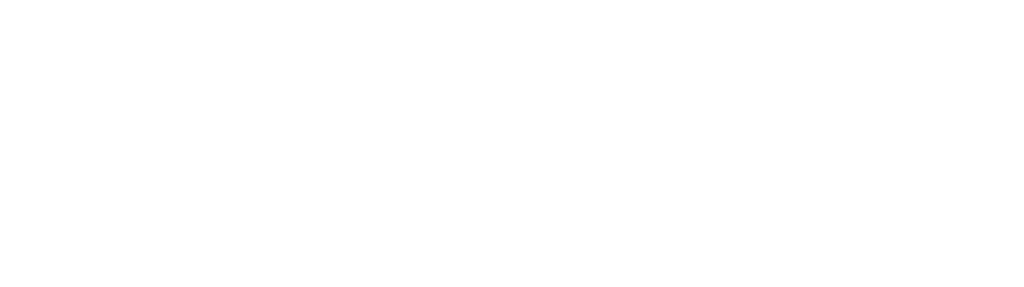- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第三十七回 伊藤俊治「芸術の再生のために」
新型コロナウィルス感染拡大に伴う入構禁止やイベント中止が続いた2020年9月から10月にかけて、先端芸術表現科20周年記念と共に私の退任展を兼ねた「先端芸術2020/アペラシオン」展を、東京藝術大学大学美術館陳列館で開催することができた。
新学期の始まりを控えた慌ただしい時期の手探り状態の展示作業だったが、23名の参加アーチスト、展覧会スタッフ、助成や協力を頂いた関係者の方々に大変お世話になり、この場を借りて深く感謝したい。
入場制限や予約システムのトラブルなど、思いがけない問題や困難が次々に襲ってくる中、関係各位の力強い連携により、展覧会に力と生命を注ぎ込むことができ、時代精神と結びついた印象深い展示と高い評価を受けたことはこの上ない喜びである。
先端芸術表現科には2000年に着任した。それ以前に多摩美術大学で1985年から教鞭をとっていたので足掛け35年に及ぶ大学教官生活となる。日本へ帰国直前まで、ポンピドゥ?センターで行われた大規模な日本展「前衛芸術の日本」に協力し、長くパリに滞在していたので、いきなり呼び戻され、あたふた教官生活に入ったことも懐かしい思い出である。
よく知られるようになった「検疫(カランティン Quarantine)」の語源は、イタリア語の「40日間」という言葉である。この言葉は1347年にベニスで起こったペストの大流行に遡る。ペストは東方から来た船が広めているとされ、潜伏期間の40日間、港外に船を強制的に停泊待機させ、やがてそれが「検疫」の意味となった。
この「検疫(カランティン)」を原題とするノーベル文学賞作家ル?クレジオの『隔離の島』(2013)がコロナ禍で再び読み始められている。19世紀末、マルセイユからモーリシャス島へ向かう兄とその妻、弟を乗せた船で、天然痘患者が見つかり、検疫に服すため、プラト島への下船を余儀なくされた。外部から見放された隔離生活が続き、疫病は島を蝕み、治る見込みのない病人は対岸の島に追いやられ、死ぬと火葬された。死と隣り合わせの極限状態を生きる人々の弱さと狂気が炙りだされてゆくが、弟だけはこの隔離の中で、新しい自由のようなものを見出してゆく。自分というものを超えた大いなる場所や見えない深遠な存在がすぐ傍らにあることに気づき始める。40日間が過ぎ、やがて迎えの船が来るが、弟は兄たちとは離れ、失踪者として新しい世界へ身を投じていった。
「あまりに多くの出来事があり、あまりに多くのものが壊れたり、別なふうにとつくり直されたりした。僕らの感情や観念がそうだし、目つきや話し方、歩き方、寝方まで変わった。死んだ者もいるし、気の触れた者もいる。これからはもうけっして以前のままではない」(『隔離の島』中地義和訳 筑摩書房)
芸術もまた以前のままではありえない。かつてル?クレジオは「芸術というものはなくて、あるのはただ医術だけだということを、いつの日か人々は知るに違いない」と言ったことがあるが、根源的な癒しの力を持つ芸術の役割に今後、新たな光が当てられてゆくだろう。「先端芸術2020/アペラシオン」展もまたル?クレジオの言葉を確認し、創造の軸を移す新たな道しるべだったと考えている。

(2020年6月 陶酔映像論)
?
写真(上):2020年9月20日?2020年10月3日東京藝術大学大学美術館陳列館にて開催された「先端芸術2020/アペラシオン」展のDM
?
マータポートによるオンライン展覧会「
会期:2020年11月9日(月) – 12月25日(金)
>>https://my.matterport.com/show/?m=XJrCf8orwpY
?
【プロフィール】
伊藤俊治
東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授 / 美術史家
1953年生まれ。
東京大学文学部美術史学科卒業,東京大学大学院人文科学研究科修了(西洋美術史専攻),多摩美大学院教授を経て現職。主要著書に『写真都市』『ジオラマ論』『機械美術論』『電子美術論』『裸体の森へ』『愛の衣裳』など。国際展覧会企画に「四次元の知覚」(オーストリア、グラーツ),「移動する聖地」(東京)「デジタルバウハウス」(ドイツ,ケルン)など多数。