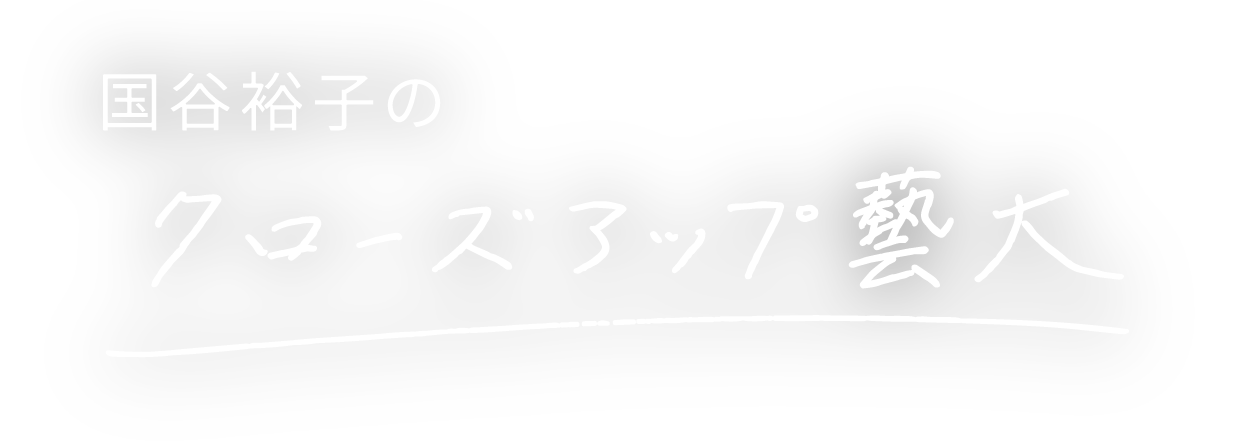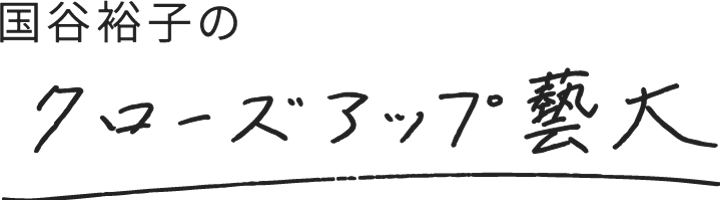第十一回 高木綾子 音楽学部器楽科(フルート)准教授
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。東京藝大の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。月に一回のペースでお届けします。
>> 過去のクローズアップ藝大
第十一回は、音楽学部器楽科准教授で、フルート奏者の高木綾子先生。令和2年3月、レッスン室にてお話を伺いました。
※この取材は東京都の外出自粛要請が発表される前に実施しました。
【はじめに】
フルート奏者と言えば優しい、きらびやかな女性が吹いているというイメージが付きまとう。それはフルートの音色が柔らかく小鳥のさえずりのようだったり、CDのジャケットにエレガントな女性奏者の写真が載っていることと深い関係があると思います。写真で見る高木先生はまさにそのイメージ通りでした。
大学3年で早々とCDデビューのチャンスを掴み、将来の子育てを考えてオーケストラに入るのではなくスケジュールの柔軟性のある大学で教鞭をとる仕事を選択し、演奏活動も活発に行ってきました。32歳で長男を出産、育休を一度も取ることなく3人の子供をとても計画的に生み育てているスーパーウーマンとして紹介されることが多い。
仕事も私生活も自分のやりたいことをやっていけるように努力を続けてきたという高木先生とのお話は新型コロナウィルスの影響から始まり、コンクールの挑み方に続きました。どうしたら大舞台に強くなれるのか。そして対談が進むにつれ話は言葉の大切さにも拡がりました。
国谷
高木先生は今、大変なのではないですか? 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、全国の学校が臨時休校でしょう。お子さんは小学生ですよね?
高木
そうですね。でもちょうど大学が入試期間中で授業が無いということもあって、私が家に居られる日は家に居て、大学に来なきゃいけない日は主人がリモートワークで自宅勤務して、入れ替わりで。
国谷
コンサートもキャンセルになっていると聞きますけれど、影響はありますか?

高木
3月前半まで入試期間中だったので、コンサートの予定はあまり入れていかなったんです。3月後半以降のコンサートは、主催者が延期や中止の可能性を探っているようです。
国谷
お子さん達への影響はどうでしょうか?
高木
状況は子どもたちなりに理解しています。ただ、どんどんストレスが溜まってきていますね。午前中は宿題をさせて、お昼ご飯を食べた後に少し散歩とか、買い物がてら公園で1時間くらい遊ばせて、という感じです。
国谷
高木先生のように、3人のお子さんがいながら演奏活動もして、大学で教員もして、という方はなかなかいらっしゃらないので、今までもダイバーシティとか子育てについてインタビューを受けられることが多かったと思います。もちろん、そちらも大事ですけれど、あえて、今日は違う話をおうかがいしようと思っています。
東京藝術大学ダイバーシティ推進室のインタビュー記事はこちら
>> http://diversity.geidai.ac.jp/interview/takagiayako/
演奏家の活躍の場も多様に
国谷
高木先生のキャリアを見せていただいたら、あまりにもたくさんコンクールの実績があってびっくりしました。ところがインタビューを拝見すると、コンクールの実績なしにCDデビューできたとおっしゃっていて。
高木
はいはい(笑)。
国谷
演奏家としてコンクールは登竜門というか、自分のやりたいことをできるようになる一つの大きなきっかけですよね。コンクールに強くなるにはどうしたらいいのでしょうか?
高木
コンクールに強くなるには…ですか。
学生たちにも言っているんですけれど、昔に比べて今はコンクールの数が多いんですよね。私の師匠の金昌国先生の時代は、数年に1回しかフルートのコンクールがないという感じでした。日本音楽コンクールも当時はフルートが審査対象になるのは8年に1回だったし、ジュネーブとかミュンヘンとか海外でも数年に1回という世界でした。
だから昔の人たちはコンクールに命をかけていたんです。その時期に合わせて準備をして、自分を高めて。今は、年間5、6回もあるから、とりあえず数を撃てという感じになっている。学生たちもみんなコンクール慣れしてしまっているので、少しだらけた雰囲気を感じます。
国谷
これがだめなら次があるさ、みたいな。
高木
そうなりますよね。だから、コンクールが数多くあることが学生のためになっているかというと、疑問なところもあります。入賞すると自信にはつながるので、多くの人が入賞するのはいいことだと思うんですけれど、でも蓋を開けてみれば、結局本選に残るのはだいたいいつも同じメンバーなんです。1人が国内のコンクールの上位1、2、3位を3、4個持っているのが当たり前。さらに言うと、大きなコンクールで3つぐらい1位を獲っても就職出来ないのが当たり前。だからそういう意味では、コンクールだけが将来のことを決める世の中ではないのかなって。
国谷
なぜこんなにコンクールが増えたのでしょう? フルート人口が増えているからですか?
高木
フルート人口は増えてはいないと思います。私たちが学生の頃は、私立の音楽大学だと1学年に80人位、フルートの学生がいると言われていた時代なので、それと比べると、フルートを学ぶ学生は減っていますね。
国谷
面白い現象ですね。学生数は減っていて、コンクールは増えている。チャンスはあるけれど1位を3回獲っても就職できない。
高木
ものすごく厳しい世界ではあると思います。ただ、今の音楽業界では、いろんな形で活躍できる場が増えています。
私たちの時代はやっぱりCDを出すことや依頼を受けてコンサートで演奏することが、プロの証みたいなところがありました。でも今は、自分でホールを借りるとか、レストランライブ、イベント、Youtuberみたいな動画配信で活躍する人もいて、自分の演奏を人に聴いてもらう機会はものすごく増えていると思います。
国谷
そうですよね。自分でイベントを企画して場所を借りることもできますし、周知にしても自分のネットワークとか、SNSを利用してもできます。
 レッスン室の壁には賞状やデビュー10周年記念リサイタルのチラシが
レッスン室の壁には賞状やデビュー10周年記念リサイタルのチラシが
チャンスを無駄にしないために結果を出す
国谷
高木先生は在学中にCDデビューをされました。その時にコンクールの受賞歴がないということで、「私はコンクールで勝ちます!」と、とにかく矢継ぎ早に受けて国内の4つの大きなコンクールを制覇されたという。
高木
いや、そういうわけでも…。CDデビューのきっかけは、プロデューサーさんが私の出身地、愛知県豊田市のコンサートホールに来ていて、私が出るコンサートのチラシがたまたま目に留まったんですね。ホールの事務局の方も「この子はスーパースターですよ!」と薦めてくださって。ちょうど「Jクラシック」というジャンルが話題になっていたこともあってCDデビューのお話をいただいたわけですが、私はまだ大学3年生でしたし、賞を獲っていない学生がCDデビューをするような時代ではなかった。
国谷
そんな大それたこと、できませんって。
高木
自分でも学生の身分でCDデビューしていいのかよく分からない。もちろん五嶋みどりさんのように、小学生の頃からCDデビューするような人もいますけれど、この大学でそれが許されるのか分からない。そこで指導教員の金先生にご相談してみると、「この世界は一度CDデビューを断ると、あの子はCDデビューしないという噂が立つことがある。今ならデビューしてもいいというときに、そういう噂が流れているととても不利になってしまうから、ここは断らずにやってみなさい」と、許可して頂いたんです。だだし、学業とか自分の練習の妨げにならないようにって。
お話をいただいたのは大学3年生、録音したのは4年生、発売したのは大学院に入ってから。4年生のときにコンクールで2つぐらい優勝したので、CDが出たときにはいくつかタイトルを持っていたんです。でも、CD出す前から、「CDデビューするらしいよ」「なんであの人が?」というような噂話は、あっという間に広まるんですよね。そういう後ろ指を指されて生きていくのも嫌だし、手っ取り早く人から認められる方法はやっぱりコンクールで入賞することだろうと。せっかくCDデビューのチャンスをもらったんだから、それを無駄にしないような結果を自分で付けていくしかないと思って、コンクールでタイトルを獲ることに集中した時期はあります。

国谷
そういう雰囲気のなかで実力を試すためにあえてコンクールに打って出る。CDデビューがない状態と比べると、むしろプレッシャーは強いわけですよね。
高木
そうですね。
コンクールでは自分をプロデュース
国谷
演奏家とスポーツ選手ってちょっと重なるところがありますよね。みんな切磋琢磨して一生懸命練習して、体調を整えて、どうしたら認められるだろうかって。その瞬間瞬間にベストのパフォーマンスをしなければいけないという意味では似たところがある。実力があっても、その場に行ったときにベストのパフォーマンスをすることができない人もいます。
高木
才能はあるけれどなかなか勝てないという人は、私が教えている学生の中にもいます。でも…まあ私もその当時の審査員たちがどういうふうに私を見ていたかは全然わからないんですけれど…。とにかく自分の“音楽観”みたいなものをものすごくアピールしていたと思います。今は演奏しながら「この楽曲の構成は…」とかいろいろ考えちゃいますけれど、若い時は若いなりの熱意みたいなものが演奏に出て行く。その熱意は魅力的だと思うけれど、聴いてるほうはただ熱意を聴いているだけだと疲れちゃうじゃないですか。なので、そこの加減はプログラミングとかで工夫する。その時代ごとの背景をちゃんと入れ替えることを、コンクールのときは意識していたと思います。自分のプロデュースとか、演奏の中身というかプログラミングのプロデュースは、考えていたほうが聴き手に伝わりやすいんじゃないかなと。
国谷
「時代ごとの背景を入れ替える」というのがよくわからないのですが…。
高木
私たちが演奏する曲は、作られた時代が全然違うものなんです。バロックや古典、ロマン派とか近現代とか、国も違えば時代も違う。例えばドイツで生まれてフランスで勉強した作曲家もいる。作曲家が学んだ場所とか、仲良くしていた周りの人たちとか、師匠とか、同時代の作家とか画家とか、雑学じゃないですけれど、こういう時代のなかでこの人は音楽を書いていたんだなって、自分の中で膨らませるんです。
国谷
それが全部その曲の表現の中に?
高木
入っていくものだろうと私は思っています。
意識して言葉にする

国谷
高木先生のレッスン風景をビデオで拝見したのですが、「何が悪かったか“言葉”で言いなさい」ってよくおっしゃっていました。私は素人なので、演奏は間違っても演奏で返せばいいのだろうと思っていましたが、高木先生は言葉にしてほしいと。息子さんにも同じようなことをおっしゃっていました。
高木
そうそう(笑)。
国谷
言葉を使って仕事をする者としては、言葉にこだわっていらっしゃるのは非常に面白いなと思いました。これはどういう意図なのですか?
高木
若い頃から、よく楽譜に言葉を書いていたんです。例えば、1つの曲を物語に書き換える。曲とは全然関係なくていいんです。ここは誰と誰の出会いの場面とか、ここはどっちかが怒っていてどっちかが泣いている悲しい場面とか、自分が簡単に思い浮かべやすい物語にして書き留める。本を読むことが好きだったからかもしれません。楽譜に書いておくと、演奏しながらパッと見てすぐ気持ちがわかりますよね。楽譜に反応できるんです。
国谷
う~ん。私にはよくわからないですね(笑)。
高木
練習すれば音符は覚えられるけれど、本番では緊張して感情面で入り込めなかったりする。そんな時、言葉があれば「こういう気持ちで吹かなきゃ」って反応できる。もともとはそこから始まっているのだと思います。
次に言葉を意識し始めたのは、人に教えるようになってからです。演奏のなかで無意識にやってることってあるじゃないですか。それを人には言葉で教えるしかない。例えば、口のなかでどういう空間ができているとか、自分の息がどこに当たっているとか、どこを意識して響かせるとか、お腹の空気の持って行き方とか。そういうことを逐一言葉に置き換えて伝えて初めて、自分の吹き方がよくわかったんです。今こうやって吹いているんだってことを、自分で再認識するっていうんですかね。教えているときにそういうことを学んだんです。
だから学生たちにも、雰囲気で吹くのではなく、“どうやって”の部分、“何を伝えたいのか”の部分を言語化するように指導しています。あとは、間違っている場所は毎回間違えるから、口で言わせる。ただの音間違いとして認識するんじゃなくて、ここがこう間違っていると言葉で認識すると、直しやすいというか。
国谷
言葉というのは非常に不思議です。私は帰国子女なのですが、アメリカから帰って来て日本語で仕事をしなければいけなくなったときに、英語のニュースを聴いて日本語に直す練習をしていたことがあります。その時もただ単に頭の中で直すよりも実際に口に出して言ったほうが、言葉が自分のものになるという感覚がありました。あるいは言葉を書きながしゃべるということも、同じようにその言葉が自分のものになるという感覚がありました。今先生がおっしゃったことで、繰り返しミスをする部分とか、何を伝えたいのかを言葉にさせるというのは、より深い認知につながる可能性があるのかなと思いました。
高木
無意識でやることと、意識をして言葉に出してやるということでは、かなり差が出てくると思います。
楽器をやっていると、慣れているから音を鳴らすことはできる。でも言葉で言うというのは、楽器を吹く脳と違う部分の脳をプラスαで使うことになるので、もう一個積み重ねて確信が増えていくと思います。例えば、「楽譜を読む」ということでも、楽器で音を出すのではなく全部音名で言うということを学生によくやってもらいます。口で活舌よく言えれば、指は勝手に動く。実際に音で認識して指を動かしているよりも、音名を言って音を認識したほうが指がよく動くんです。
国谷
音名を声に出すことで指がよく動く、繊細につながっているのでしょうか。
高木
多分、何かあるんだと思います。
 年季の入った練習用の楽譜
年季の入った練習用の楽譜
| >>?次のページ 精神面は本当に弱いので… |
|---|
- 1
- 2